
どうも!KENT(@kentworld2 )です!
もうすぐ2010年代が終わりを迎えようとしています。
振り返ってみると2010年代も初期と後期では価値観が大きく変わりました。
それは任天堂に関しても例外ではありません。
むしろ、この10年間は任天堂史上最も変化があったのではないでしょうか?
少なくとも任天堂を20年以上ウォッチャーしているぼくはそう感じています。
2010年以前の任天堂はどんな感じだったのか?

そもそも、2010年以前の任天堂はどんな感じだったのでしょうか?
簡単にまとめると、子供・ファミリー層に偏りすぎていました。
「ゼルダの伝説」「ファイアーエムブレム」などのゲーマー向けタイトルはありましたが、若者には届かないような売り方をしていたんですよ。
プロモーションはTVCM中心で、インターネットでの露出は公式サイトの立ち上げくらい。
社長が訊くなどの企画はありましたが、カウントダウンサイトなど派手なことはしていませんでした。
ゲーマー向けタイトルにしてもオールドファン向けで、色気はほとんど感じられません。
その結果、若者ゲーマーの話題はPS3/PSPソフト関連ばかり。
任天堂ハード向けになると一部のサードパーティ製タイトルくらいしか話題になりません。
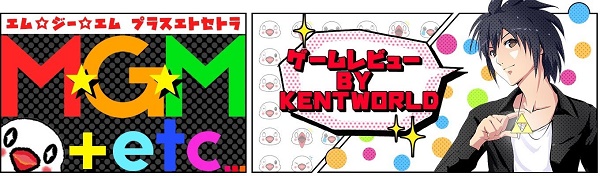
そんな中、当ブログでは2010年以前も任天堂関連の話題をよく取り扱っていましたが、肩身は狭く感じていました。
だって、ネット友達の多くは任天堂に無関心でしたから。
無理もありません。任天堂自身が若いゲーマー層向けのタイトルを発売せず、プロモーションも怠っていたのですから。
そんな任天堂ですが、2011年から少しずつ若いゲーマー層を取り込むことに成功します。
一体、どのように若いゲーマー層を取り込んだのでしょうか?
ここからは20のキーワードにスポットを当てて語っていきます。
2011年

前述の通り2010年以前の任天堂はインターネットでのプロモーション展開が控えめでした。
それ故にインターネットをよく利用する若者の間ではほとんど話題になりません。
そんな中、任天堂は2011年5月にTwitterアカウントを立ち上げます。
内容の方は公式サイトの更新情報が中心でしたが、これは大きな出来事に感じました。
というのも2011年の時点で若者の拠点はTwitterになりつつあったからです。
公式サイトの更新情報中心とは言え、若者の目に任天堂関連の情報が飛び込んでくるきっかけが生まれたのは大きなことに感じます。
ニンテンドーeショップ

2011年6月、ニンテンドー3DS(以下、3DS)の発売に合わせてオンラインストアのニンテンドーeショップが立ち上がりました。
特徴的なのが、以下のサービスを1つにまとめたこと。
・ソフト情報の閲覧
・体験版の配信
これらのサービスはWii時代も行っていたんですが、「Wiiショッピングチャンネル」「みんなのニンテンドーチャンネル」といった別々のサービスに分かれていたんですよ。
そのうえブラウザベースのソフトである関係で動作が遅く、他ハードのオンラインストアと比べて不便な印象でした。
それだけに初めてニンテンドーeショップを触った時はどれだけマシに感じたことかw
「任天堂もようやく他ハードに追いついたか」
当時はそんな感じで感慨深く感じていたのを覚えています。
ニンテンドーダイレクト

2011年以前の任天堂は情報を発信してもメディアから曲解して情報を取り上げられることが多くありました。
それ故にインターネットをよく利用する若者の間ではイメージが悪く、敬遠されがちな状況だったんです。
そんな中、2011年10月に大革命を起こします。
それがニンテンドーダイレクト!
ニンテンドーダイレクトは任天堂自らが最新情報を「直接!」お伝えするインターネット向けの映像コンテンツになります。
この番組の凄いところは、リアルタイムで最新情報を入手できることです。
それまで任天堂の最新情報は不定期に更新される公式サイトや新発売のゲーム雑誌頼みだったんですよ。
それがニンテンドーダイレクトのおかげでユーザーの間にリアルタイムで最新情報が届くようになりました。
おかげで配信直後はTwitterやブログなどで任天堂関連の話題で持ちきりになり、若者の目にも触れやすくなります。
費用対効果も良いので、若者の関心を掴むという意味ではこれ以上ないくらい効果的な施策なんじゃないでしょうか?
その影響からかニンテンドーダイレクトは2019年になった今でも続いています。
2012年
お色気
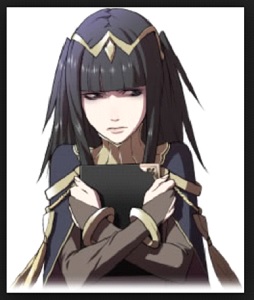
ニンテンドーダイレクトの影響でインターネットでの露出度が高まった任天堂。
しかし、肝心のコンテンツは若者ゲーマー向けとは言えませんでした。
厨ニやお色気要素が強いゲームが有り触れている中、任天堂はというとデフォルメ系か古臭いデザインのイケメンキャラが出てくるゲームばかり。
そんな中、2012年4月に大きく殻を割ったタイトルが発売されます。
それがファイアーエムブレム覚醒!
3DS向けに発売された本作は従来の古臭いキャラクターデザインを一新し、スタイリッシュなデザインにリニューアルされたんです。
さらに後述のダウンロードコンテンツではお色気要素を盛り込むという有様w
「ファイアーエムブレム」シリーズ単独で見てもこの変貌は衝撃的だったのを覚えています。
それ以降、「ファイアーエムブレム」シリーズはもちろん、Switch「ゼノブレイド2」などでもお色気要素が盛り込まれ、任天堂ゲームでも珍しくなくなりました。
ダウンロードコンテンツ(追加コンテンツ)

2012年以前の任天堂ゲームは買い切り型を貫いていました。
「一度ゲームを購入したらそれ以上追加の課金をしなくても良い」と言えば聞こえは良いかも知れません。
しかし、逆に言えば追加の課金をして”おかわり”することも出来なかったんですよ。
他ハードではとっくの昔に有料ダウンロードコンテンツによる追加ステージや衣装を続々と配信していただけに「遅れている」と思っていました。
そんな中、任天堂も3DS「ファイアーエムブレム覚醒」で初となる有料のダウンロードコンテンツを配信します。
初期に配信されたダウンロードコンテンツはイマイチだったので反発がありましたが、その後は試行錯誤して徐々に改善。
今では配信するダウンロードコンテンツの大半が良心的と言われるようになりました。
ダウンロードカード

2000年代終盤、ゲーム機の内蔵データが膨大になった関係でパッケージタイトルのダウンロード版が各ハードで展開されます。
特に話題となったのが、PSP go。
本ハードはUMDディスクドライブを搭載しておらず、ダウンロード版のみ起動できる仕様となっています。
登場するのがあまりにも早く、悪い意味で話題になってしまいましたが、時代の先を行っていたのは確かです。
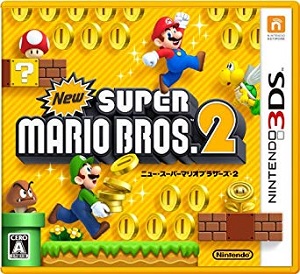
それから3年後の2012年7月、任天堂も3DS向けパッケージタイトルのダウンロード版を配信するようになります。
この点だけを見ると他社の後追いに感じますが、任天堂ならではの施策もありました。
それがダウンロードカードの店頭販売!
同時期、任天堂は店頭で対象タイトルをダウンロードできるカードを販売することにしたんです。
しかし、当時は懐疑的な目で見られることも多くありました。
「わざわざ店頭で購入してからオンラインストアでコードを入力してダウンロードするって二度手間じゃん?」と。
が、店頭でダウンロードカードを販売することでユーザーの目に止まる機会が増えたうえ、小売にも多少の恩恵を受けました。
そこまで大きな売上にはなっていませんが、ダウンロード版に馴染みのないユーザーを呼び込むためには良い施策ではないでしょうか?
ゲームソフトの更新データ

ソフトウェアの内容を無償でアップグレードするアップデート。
2010年以前の任天堂ソフトではデータ修正程度の役割しか果たしておらず、要素が追加されるなんてことはありませんでした。
ところが2012年に発売された3DS「とびだせ どうぶつの森」ではアップデートで発売後にも要素を追加していく半運営式を採用。
それ以降もWii U「スプラトゥーン」など発売後に要素を追加していく半運営式を採用したゲームが続々と発売されます。
ちなみに任天堂は”アップデート”と表記することはありません。”更新データ”という分かりやすい表記を採用しています。
HD

2000年代後半、PS3/Xbox 360といったHD機が発売になりました。
これらのゲーム機はHD画質に対応しており、より高解像度なゲームを楽しむことが出来たんです。
対して任天堂ハードになると2012年になってもSD画質のゲームしか出していませんでした。
そんな中、2012年12月に発売されたWii UはHD画質にも対応。
任天堂も晴れてHDゲームデビューを果たすことになります。
しかし、HDゲームの開発は難しく、それが要因でWii Uは思うようにソフトを揃えられませんでした。
任天堂は大手ゲームメーカーが飲んでいた苦汁を6年遅れて飲むことになり、赤字転落の要因になってしまいます。
Miiverse(ミーバース)

2000年代後半、TwitterなどのSNSが人気を博します。
そんな中、任天堂はMiiverse(ミーバース)という独自のSNSを2012年12月に発足。
まずはWii U向けに展開し、2014年からは3DS向けにも展開します。
内容の方はイラストも描けるTwitterと言った感じで、任天堂らしいアットホームな作りとなっていました。
しかし、ユーザーが増えてからは民度が悪化。2017年には早くもサービスが終了してしまいます。
人によってはイメージが悪いサービスかも知れませんが、Wii U「スプラトゥーン」のブレイクに一役買ったのは確かです。
2014年
キャラクターIPの活用

2014年以前の任天堂はキャラクターIPの活用に消極的でした。
「ポケットモンスター」などの例外はありますが、マリオやドンキーのキャラクターIPを活かすことはほとんどなかったんです。
ところが2014年以降はキャラクターIPを積極的に活用していきます。
特に大きな変化を見せてきたのが「星のカービィ」。
2014年以降は一番くじ、コラボカフェなどが展開され、関連グッズも洪水のように発売されました。
2020年にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が展開されるなど、さらなる盛り上がりを見せようとしています。
ニャニャニャ! ネコマリオタイム

2014年5月、任天堂は新たなインターネット向けの映像コンテンツを展開します。
それがニャニャニャ! ネコマリオタイム!
子供向けの映像コンテンツで、最新ゲーム情報を分かりやすく紹介する番組になります。
位置付け的には1990年代に放映されていた「スーパーマリオクラブ」みたいな感じでしょうか。
シーズンパス
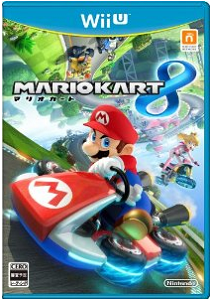
2012年から展開されるようになったダウンロードコンテンツ。
2014年になるとそれをさらに突き詰めた施策を取るようになりました。
それがシーズンパス!
今後配信が予定されているダウンロードコンテンツの使用権利を配信前に購入するシステムになります。
第一弾となったのがWii U「マリオカート8」で、発売前に複数のダウンロードコンテンツを一括購入することが出来ました。
その後も「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」「ゼノブレイド2」「大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL」など、ゲーマー向けの大作ゲームでは必ずと言って良いほどシーズンパスを採用するようになります。
セール

任天堂は値下げを嫌う企業だったりします。
廉価版を発売することは滅多にありませんし、ゲームソフトのセールも消極的でした。
ところが2014年頃からニンテンドーeショップにてセールを行うようになります。
と言っても50%OFFなど大胆に下げることはせず、せいぜい20%OFF程度ですが、あの任天堂がセールを行うようになったのはインパクトがありました。
ちなみに2016年からはハッピープライスセレクションという3DS向けの廉価版シリーズを発売するようになります。
2015年
オープンワールド

任天堂の3Dゲームと言えばリニア式か箱庭式が中心でした。
3D空間を自由に動けたとしても中規模程度に留まり、見えているところすべてに行けるゲームはほとんどなかったんです。
それが2015年4月発売のWii U「ゼノブレイド クロス」ではオープンワールド形式を採用。
見えているところまで自由に行けるのはもちろん、好きなルートから攻略することが出来ました。
その後はSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」を2017年に発売。
オープンワールドゲームの新たな基準を作り上げることに成功します。
スプラトゥーン
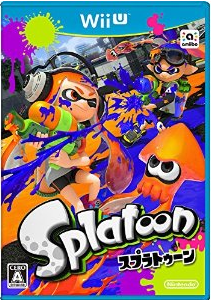
2015年5月。任天堂は空前の新規IPを生み出すことに成功します。
それがスプラトゥーン!
TPSをカジュアルにしたようなゲーム性が若者を中心に人気を博します。
運営式であることもあってSNSとの相性も抜群で、それまで任天堂がなかなか取り込めなかった層にも爆発的な人気を博しました。
トピックス

2015年12月、任天堂はトピックス というサービスを立ち上げます。
分かりやすくというと、任天堂関連の新情報をブログ形式で取り扱うような感じです。
公式サイトやニンテンドーダイレクトでは伝えきれない情報が分かりやすくまとまっているので、情報ソースとして使いやすく感じます。
2016年
スマホゲーム

2016年3月、ついに任天堂もスマホゲーム事業を展開します。
第1弾となったのが「Mii tomo」。
残念ながら不発に終わってしまいましたが、第3弾となる「ファイアーエムブレム ヒーローズ」は世界的な大ヒットを記録。
また、任天堂単独の企画ではありませんが、2016年7月に配信された「Pokemon GO」は空前の大ヒットを記録します。
それまではコンシューマーゲーム専門だった任天堂ですが、2016年以降はスマホゲームメーカーとしても人気を博すのでした。
2017年
ニンテンドースイッチ

2017年3月、任天堂の新型ゲーム機「Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)」(以下、Switch)が発売になります。
本ハードで特徴的なのが、据え置き機と携帯機のハイブリッド型であること。
つまり、据え置き機としてはもちろん、携帯機としても活用することができるんです。
その影響で据え置き機向けと携帯機向けのタイトルが統合。
リソースを分散することなくソフト供給ができるようになりました。
その影響もあってWii Uのようなソフト不足にはならず、コンスタントにヒット作を投入していきます。
今では任天堂ハードの中でも特に好調な売上を記録するほどの人気ゲーム機にまで上り詰めました。
Indie World

Switchで大きな特徴となっているのがインディーズゲーム市場の活性化になります。
その大きな役割を担っているのがIndie World(インディーワールド)。
Indie Worldはブログや映像コンテンツを通じてSwitch向けインディーズゲームの魅力を伝えていくサービスになります。
Switch向けのインディーズゲームが盛り上がっている理由は数あれど、Indie Worldの影響は大きいのではないでしょうか?
2018年
オンラインサービス

2018年9月、任天堂はSwitch向けの有料サービス「Nintendo Switch Online」を発足します。
それまでの任天堂ハードではオンラインプレイを無料で楽しめましたが、2018年9月からは定額料金が必要になったんです。
その代わりオンラインサービスの質は向上し、発売済タイトルのアップデート回数も増えました。
定額料金が必要になったことでハードルは上がりましたが、サービスの向上はゲーマー向けという観点で見ると利点に感じます。
Nintendo Creators Programの廃止

任天堂ゲームの動画配信を行う場合、2018年以前は「Nintendo Creators Program」というサービスに申請を行う必要がありました。
しかし、2018年12月末日に終了。
ガイドラインに従えば誰もが任天堂が著作権として所有しているゲームの動画配信を行えるようになりました。
若者のゲーマー層を取り込むうえでユーザー間の動画コンテンツは必要不可欠ですから、これは大きな出来事に感じます。
全体のまとめ

以上!2010年代に大変貌を遂げた任天堂が行った20の施策でした!
かつての任天堂を知る者からすると最近の変貌ぶりは感慨深く感じます。
あれほど若いゲーマー層に敬遠されていた任天堂が今では普通に人気を博していますから・・・。
それだけこの10年間に行った施策が功を奏したと言っても良いでしょう。
もちろん、他ハードと比べて遅れを取っている部分もまだまだありますが、10年前を思うとだいぶ改善されたように感じます。
少なくとも国内市場では以前よりも強固な立場になったのではないでしょうか?
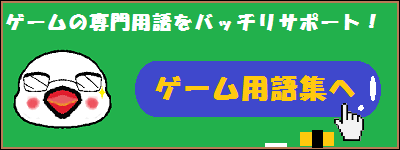
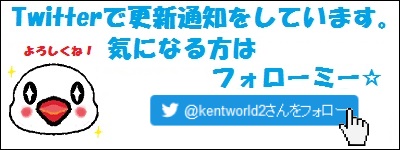
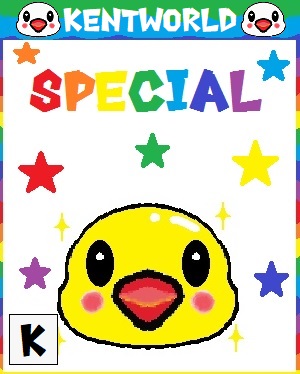








そっか、kentさんは2000年代はまだ20歳そこそこだったんですね
当時既に良い歳のおっさんゲーマーだった私は特に任天堂に距離感は感じませんでした
マニアっぽいゲームはPSで、王道は任天堂で使い分けてましたし、何なら今よりも住み分けが明確で楽だった印象すらあります
任天堂は遅れているというよりどこまでも我が道を行くというか、むしろ遅れている人達に合わせて歩みを進めているような気はしました
何せ対象は子供でも大人でもなく『全年齢』ですからね
人はこのサービスは自分向けでない、と感じてしまうとそっぽを向いてしまいますから(結果的にマニア層がそっぽを向いてしまいましたけれどw)
やりたいことと時代が噛み合っていない印象はありましたね
そう考えると今は(珍しく)歯車が噛み合って良い感じで進んでいる気はします
具体的な年齢は控えますが、当時は中間的な年齢層に大きな穴が開いていました。今はだいぶ埋められた印象で、コンプレックスも改善されたんじゃないかと思います。
確かに2010年以前の任天堂は保守的で藤子アニメのような古臭さがありましたね。
この2010年は個人的にゲーム離れしてた時期で、弟のおかげでゲーム好きに復帰した経緯があるのですが、それだけに限らず陰では任天堂のイメチェンがあったのかもしれませんね。
ニンダイは私がより任天堂ファンになった一大要因だと思います。もう今は生きがいの一つになってますよ♪
FE覚醒といえば、良くも悪くもお色気とDLCのきっかけになったゲームですね。
サーリャちゃんwww
ダウンロードカードの販売は最初、バカにしてましたけど、プリカの金額が微妙に足りないときやクレカを持ってないときはほんとに助かりました!
それに私はフルプライスのゲームのDL版を買う抵抗をDLカードがなくしてくれましたよ。
言われてみれば、アプデって任天堂は使わないですね。アプデってプログラマ用語っぽいところもあるので“更新データ”って確かにキャッチーです。
HD開発は当時は苦戦してましたねwww
WiiのツケがUのときにぶち当たってしまいました?
今、考えるとSIEと違ってソフト開発も重視しなくちゃいけない任天堂が3DSとWiiUの2機種にソフトを共有し続けるのはなかなか酷なことをしてたと思います。今はSwitch1本化の影響で去年から軌道に乗り始めた感じですね。
キャラIPの有効活用は小学生の頃から夢みてたことなので、嬉しかったな〜。
amiiboもこのキャラIP活用の一環だと思ってます。
シーズンパスはユーザによっては抵抗もあるみたいですが、ソフト開発においては任天堂はとても信頼してるので、感謝と将来のお楽しみのためにおもしろかったゲームはFEシリーズを中心に積極的に購入してます!
セールが積極的になったのは5年前ぐらいでしたっけ?
Switchあたりになってからはファースト中心に各社がことある時期にセールしてますねwww
私は期間限定で購入を急かされるのが嫌いなのとほんとに興味あるゲームはセール関係なく買うので、セールはあまり興味を持てないのですが、Steam中心にライバルがやってるので一般的にはいい試みだと思います。なんだかんだでたまたまセールになってたから買ったというケースもありますしねwww
スプラやマリメの成功で若年層に興味を持たせる試みがようやく成功した感がありますね。
インディーワールドは個人的にインディーゲームを見直したきっかけになりました。
ディグ2やセレステ、ホロウナイトは良いゲーム体験でした!
オンラインサービスは今後の発展がまだまだ必要ですね。
ケントさんのブログもここ最近は変化の連続で毎回、私は「ホゲェ〜」と驚いてますが、毎回、特にケントさんチョイスのゲーム最新情報を楽しみにしてるので相変わらずよろしくです。
私は特に変化を希望してないのでコメントをしなかったのですが、たとえメインをtwitterにしてもコメント返信は1記事に1回はしてくれると私は嬉しいな?
私のコメントは毎回、偉そうだと思いますがどうかよろしくね☆
そうそう、藤子アニメ。素晴らしい例えだと思いますw
2010年からの大変貌は印象に残っていますよ。ニンテンドーダイレクトが与えた影響はあまりにも大きいです。
FE覚醒も当時は衝撃的で賛否が分かれていましたね。ダウンロードカードも今や定番化していて、新しいことを取り組む時は賛否がつきものなのかなと思いました。
当ブログとしてはアップデートという用語に統一したいんですが、任天堂は更新データと分かりやすい表記にしていてさすがです。
HD開発は大変なので、技術が発展するからにはいつかは苦汁を飲まないといけないんですが、良くも悪くもWii Uの頃に沢山の膿を出した気がします。
最近は任天堂キャラクターを街で見かけることも珍しくなくなりました。
シーズンパスは開発者を追い込むきっかけにもなるし、ユーザーの囲い込みとしても有効なので良いビジネスモデルに感じます。
セールはいつの間にか定着しましたね。Switchでは毎週のようにやっていますからw
インディーズゲームへの取り込むもここ最近は印象に残っています。今やインディーズゲーム=Switchになってきたんじゃ?
ブログ運営に関してはコミュニケーションの選択肢が増えたくらいなので、自分に合うものを選択して頂けたらなと思います。もちろん、トモフミさんのコメントは出来る限り返信していきますよー。
僕は2011年の時にはPS3もPSPを持っていなかったので、ニンテンドーeショップをはじめをしたニンテンドー3DSのサービスの多様化には、携帯機でここまでできるようになったのかと思い感動しました。3DSは結果的に任天堂そしてCSゲーム機の中心として数年間活躍し続けたのは、間違いなく多様なサービスをそこまで不自由なく実装できる高性能さを3DSが持っていたからだと思います。2011から2016年はCSゲーム業界にとってスマホゲームの台頭もあり存続の危機すら少し漂っていましたが、何とか任天堂やSIEは乗り越えてくれて本当に良かったと思います。
3DSはネットワーク機能が大幅にパワーアップしていましたもんね。
まあ、それでもスマホなどの進化には追いつきませんでしたが、DSからの進化は印象的です。
10年代は任天堂は大きな苦労と共に変化をした年代ですね。確かに任天堂はセールを余りしませんよね。Switchの2本キャンペーンもある意味セールですものね。
最近はあまりコメントをすることが少なかったですけど、知らない間にkentさん大分考える事があったみたいですね。でもkentさんのゲームへの思いやブログに対する思いも知れて良かったです。
骨折の関係でスマホゲームやマリオメーカー2やFEを片手でプレイをすることが多かったですけどようやくギプスを外したので暫くしたら普通に出来るはず。
おお!骨折も治ってきましたか!良かった・・・
任天堂は他社と比べてセールに消極的ですが、それでも近年は増えてきました。
最近はブログの台所事情ばかり語っていてお騒がせしていますm(_ _)m
正直インディーワールドは不満点しかありません
更新頻度がにゃにゃにゃマリオに比べて低いし、旬をすぎてる(と感じる)ソフトが多いしeshopランキングにも対して影響しない
にゃにゃにゃには頻度で劣るしよゐこには面白さで劣る
せめて海外で発表されたけど続報が全くないinto the breach、ホロウナイト続編の続報(Slay the Spireの時も相当ストレスだった)とかリリース前の情報を出すとかにゃにゃにゃとの差別化図らないと埋もれちゃうかも
あとインディーに貢献してるのはよゐこの方が圧倒的かなぁ(ふにゃべぇとか)
よゐこのチャンネル開設されたけど任天堂動画に比べると相当よゐこ好きじゃないと耐えられないくらいグダってて徐々に再生数上がらなくなってるの見ると任天堂の作り方が上手かったんだと再認識しました
ちゃぶ台アフロはビクロイ取るまでやるくらい長い目で見てもらいたかったなぁ
僕がケントワールド知ったきっかけはよゐこのインディー生活見て気になったソフトをググってたどり着いたサイトのひとつです
個人的にはIP利用の点ではネトフリかクランチロールと組んでゼルダとメトロイドのアニメ化してほしいですね(ゼルダは昔アメリカで糞アニメ化されてるけど…)
そうですね、時間がある時によゐこの方に差し替えようかなと思います。
当ブログを知ったのはインディーズゲームの記事がきっかけですか!?
どんな形で知ったのか生の声はとても参考になりますm(_ _)m
ゼルダとメトロイドのアニメ化、ぼくも大歓迎です!そのうち実現してくれないかなぁ♪
ゲーム内容もスコアアタックやタイムアタックと言ったアーケードゲームのシステムから、短時間に達成感を得られるシステムに変化した印象です。
その一方で、相変わらず変化が乏しいカービィシリーズやポケモンシリーズ等のセカンドパーティが気になります。
そうですね、その辺りは今後の課題です。ポケモンはソード/シールドに期待しています。
2010年代の任天堂はスマホゲーとの戦いだったと思います。2000年代はソニーとだけ戦ってればよかったけど、2012年あたりからガールフレンド(仮)が出始めたぐらいからCMの露出度でも若者の関心度でもソシャゲがめちゃめちゃ強くなって。
2010年台に任天堂が変化せざるを得なかった理由は色々あるだろうけど、ソシャゲ人気に家庭用ゲーム機がおしこめられてきたというのも大きいでしょうね~。
Switchが発売されて家庭用ゲーム機に風向きが変わるまでのあいだ、具体的には2012~2017年の5年ちょいぐらいは本当にソシャゲが強かった。デレマス、白猫、モンスト、パズドラ、ツムツム…他にも数えきれないくらいのソシャゲが基本無料で遊べてみんなそっち行ってましたからね。
それに対して任天堂が打った手が「逆にソシャゲの良い面はこっちも取り入れる」というのはすごく良かったと思います。半運営型のゲームや長期的にDLCを配信するゲームを増やしてユーザーの関心を保ち続けたり、任天堂自身がソシャゲを出したり。あとSNSは既存のものを使った方がラクなのでミバを廃止してツイッターに委ねたり。ゼノブレ2のブレイドは完全ガチャだったしw
今でもFGOとかは大人気だけど、一時期に比べて本当にコンシューマーゲームは持ち直したと思います。WiiU末期はもうこの先この国にはソシャゲしか残らないんじゃないかってぐらいスマホゲーが強かったですから。ダイレクト含め任天堂の変化は功を奏したと思います。情報を欲しがってる人の元にちゃんと当事者が情報を届けるって、大切だね!って。
ソシャゲーの存在は間違いなく大きいでしょうね。
もし、ソシャゲーが台頭していなかったら任天堂もここまで変わろうとしなかったでしょう。
企業というものは危機感があるからこそ変わっていくものだと思いますので。
今回は2010年代の施策というテーマでしたが、ソシャゲーが任天堂を変えた点をクローズアップするのも面白そうですね。
ここ数年でコンシューマーゲームも再評価されている印象なので、ずっと残り続けてほしいです。
揚げ足取るようであれですが、「インターネットでの露出は公式サイトのみ」ってのは違うんじゃ無いですか
90年代後半からNOMやGCどう森の合言葉サービス等々やってましたし
それらも公式サイトという括りにしていました(汗) 少し書き直します。
ニンテンドーeショップとニンテンドーダイレクトは長く続けているだけに、今となって大きな存在となっていますね。ずっと他社に遅れていると後ろ指さされていた任天堂でしたが、後発だったために先行した他社を参考にしてここまで来れたのだと今では思います。
やはり大きな変革をもたらしたのはスプラトゥーンですね。あのWiiUでTPSというジャンルであれだけの話題を巻き起こしたゲームは間違いなく任天堂自身にも大きなインパクトとキッカケを与えたと思います。
小さなことで個人的に印象的なのはセールを積極的に行うようになったことですね。2015,16年頃はとても規模の小さなセールをたまにやるくらいだったのに、ここ数年は自社のタイトルでさえキャンペーンで安く提供する姿勢には数年前から考えると驚きですよ。DL販売の規模が大きくなったことが大きいのかな?
ニンテンドーeショップとニンテンドーダイレクトは今や欠かすことが出来ませんもんね。8年前は信じられませんでした。
スプラトゥーンの人気には驚いていますよ。Twitterでの人気も高いことから任天堂が苦手とする層を取り込めているんだと思います。
ここ数年はセールが活発になりましたよね~。Switchが発売された辺りから顕著になってきました。最近はインディーズゲームのセールが凄すぎるw ダウンロード版への移行も兼ねているんじゃないかと思います。
複写機・クレー射撃の大借金からのG&Wとドンキーコング、64とGBの失敗からのポケモン、64DDからGCの失敗からのWiiとDS、Wii時代のイメージを引きずったことによるWiiUの大失敗からのスプラとSwitch
良い悪いの波があるというか、このダイナミズムこそが任天堂の面白さの根幹をなしてる気がします
分かりますよ、任天堂も波乱万丈で見ていると楽しいですw でも、いつの時代も良質なタイトルを生み出してきますよね。