
▼この記事で主に伝えたいこと
・エンディングの要素があると生まれるメリットはユーザー側には沢山ある。
・エンディング後にそのゲームから距離を置く感覚は円満退職に近い。

どうも!KENT(@kentworld2 )です!
毎週、沢山のゲームがあらゆるゲーム機、デバイスに登場します。
そのためゲームジャンルも多種多様ですが、ぼくは明確な終わりが存在するゲームが好きです。
本記事ではその理由を語っていきます。
その1:とても大きな達成感がある
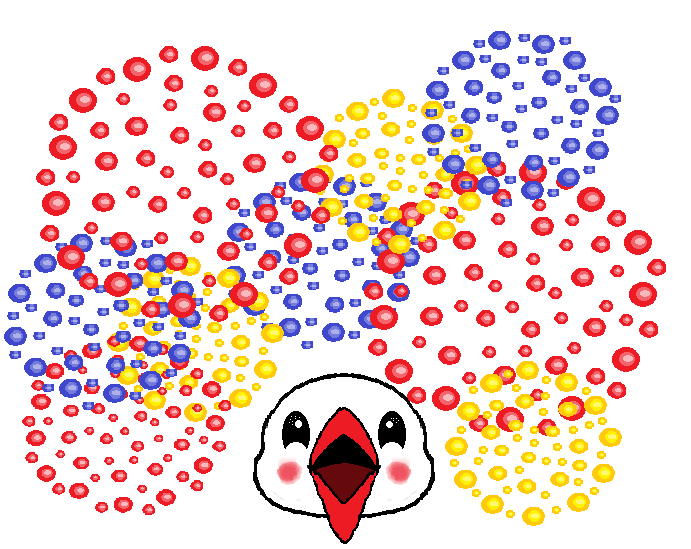
やったぁ!ゲームをクリアしたぞぉ!
そのゲームに存在するエンディングを迎えた時、ぼくはとても大きな達成感を味わえます。
ラストステージをクリアしたという事実はもちろん、ストーリーが一区切りをすることに達成感を持つんですね。
これは単独のステージをクリアする時の達成感とは比べ物にならないほど大きな物だと思います。
ゲームをクリアした!
その時に味わえる達成感は格別です。
その2:締まりが出てくる

クリアまで突っ走るぞぉ!
明確な終わりが存在するゲームの場合、そこまで突っ走りたくなります。
個人的にゲームって明確な目的があった方がモチベーションが高まるんですよね。
なんの目的もなくブラブラと寄り道をするのも楽しいですが、そればかりだと締まりがなくなってしまいます。
プレイヤーがゲームを攻略する動機付けを持たせるため、エンディングの要素があると嬉しいですね♪
その3:お得感が生まれる

あれ?エンディングを迎えたのにまだダンジョンがあるのか!?
ぼくはエンディング後の要素は100%+αという認識でいます。
そのためエンディング後に要素が追加されるとお得感を持ってしまうんです!
何故ならエンディングを迎えたらそのゲームを終えても良いものだと思っているから。
プレイヤー側からしたらゲーム内に用意されているダンジョン数は公式が明かさない限り基本的には分かりません。
なので、例えダンジョンが100あっても80個目をクリアした時点でエンディングを迎えられるようにしても気にならないんですよね。
それどころか残り20個もダンジョンがあると知ってお得に感じることが多いです。
このようにボリュームが多すぎるゲームの場合、達成率100%を迎えることでエンディングにするのではなく、50~80%辺りのところで迎えるようにした方が様々なメリットが生まれてきます。

これはリニア式のゲームはもちろん、オープンワールドゲームにも言えることです。
オープンワールドゲームはメインミッションの他にサブミッションやミニゲームが用意されています。
それらはサブ要素であってクリア必須ではないからこそ自由度やお得感が生まれてくるものだと思っているんですよね。
もちろん、メインミッションの攻略に全く絡まないようだと味気ないのである程度は連動させてほしいですが。
その4:後味が良い

明確な終わりが存在するゲームは存在しないゲームと比べて後味良く終わることが多く感じます。
何故ならエンディングを迎えた時点でそのゲームとの関係を終えたように感じるからです。
例えで言うなら円満退職のような感じ。
バックレなどをせず、会社に自分の意志を伝えたうえで業務の引き継ぎを行っての退職は実に気持ち良いです。
一方、終わりがないゲームの場合、「飽きたからやめる!」「アップデートで改悪してきたからやめる!」みたいに後味が悪い終わり方をすることがあります。
例えで言うなら会社に愛想を尽かして辞職するような感じ。
「気がついたらやらなくなった」みたいな終わり方が出来れば良いんですが、運営型で次から次へと要素が追加されるゲームの場合はなかなかそうはいきません。
全体のまとめ

以上!ぼくがゲームにエンディングという終わりを求める4つの理由でした!
ゲームにエンディングの要素が存在すると大きな達成感や締まりが出てくるし、後味が良くってお得感が生まれます。
こうして考えるとゲームにエンディングが存在することへのメリットって沢山あるんですね。
あくまでもユーザー側の話であって開発者側からしたら困る部分もあるとは思いますが、ぼくはエンディングの要素が存在するタイプのゲームが好きです。
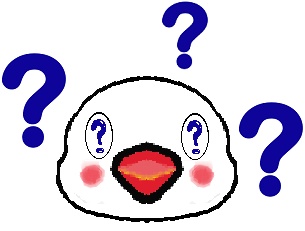
何故、ぼくがマルチプレイメインのゲームでも明確なエンディングが存在するストーリーモードを求めてしまうのか?
考えてみたところ、この記事で挙げた4つの理由が出てきました。
ストーリーモードで基本的なゲームの構造を理解してマルチプレイモードは程良くやれば良いよ♪
そんなスタンスのゲームが好きですね。
同じくオープンワールド型のゲームにしても
メインミッションがメインだからサブ要素は程良くやれば良いよ♪
みたいなスタンスのゲームが好きです。

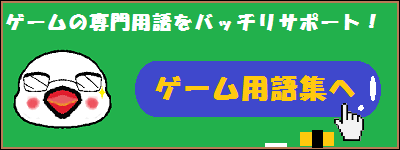
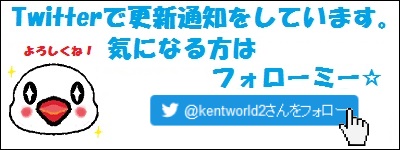
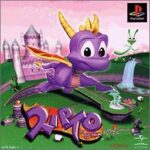



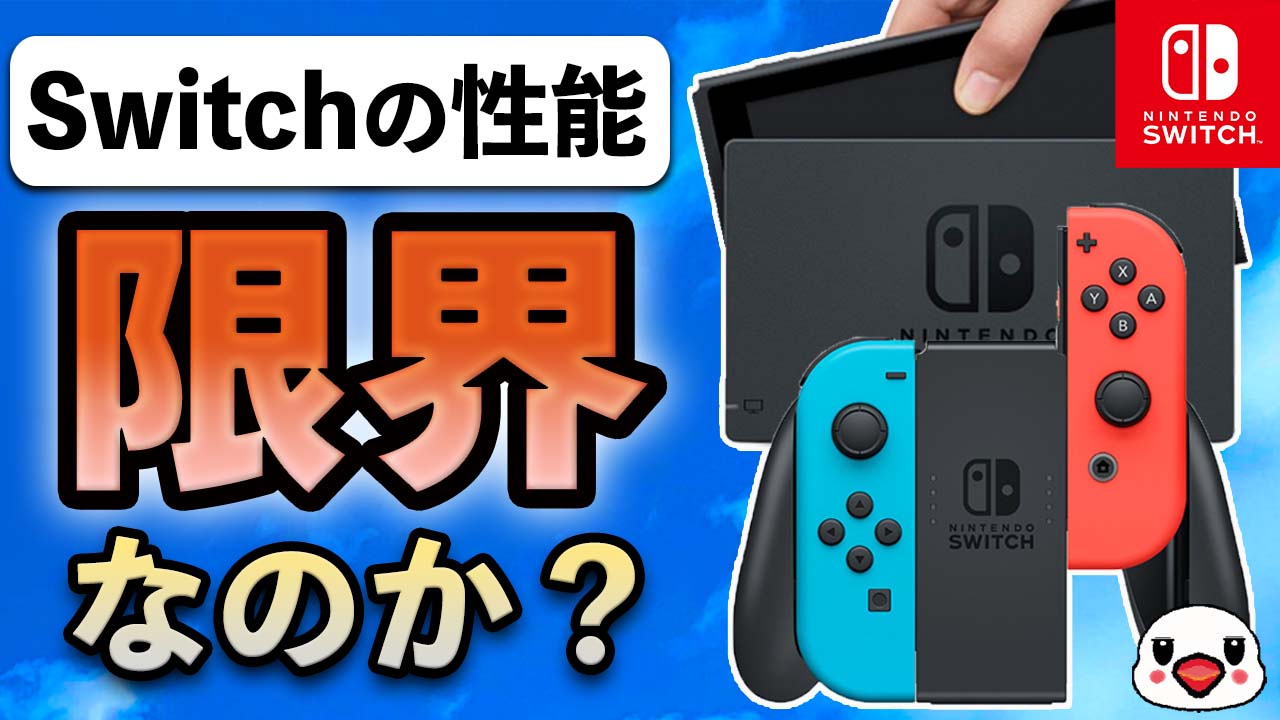



ソロプレイのゲームは
キャンペーン10時間~20時間、あとはマルチで楽しみなよ!
くらいが個人的には良いですなぁ
もうクリアまで30時間超になると
ええ?まだ終わらないのかい?サザ○ー?ってなりますねぇ
50時間超になると、俺には無理だな(笑)ってなります。
格ゲーとか対戦要素が面白ければ、なんだかんだ累計で50時間とか遊べますが、ソロで同じ様な作業をしてるとキツイキツイですわ
エンディングは腑に落ちれば良いけど、最近は「へ?」ってなるエンディングのゲームも増えてきて、制作者の自己満足を見せられて終わりの時は
(-_-;)う、うーんってなります(笑)
最近はエンディングよりも、尖ったゲーム性に触れるか?が重要になってきた気がします。
sinnerで久々にゲームをクリアしたんですが、エンディングはイマイチだったけどゲームが尖っていたのでOK?です。
ぼくも同じくらいのプレイタイムが理想的に感じますねー。
50時間はジャンルにも寄りますがアクション系だとキツイw
RPG系だと何故か知らないうちにそれだけの時間が経っていますw
エンディングは特に欧米製だとよく分からないことが多いですねー。
せっかくゲームとしては面白いにエンディングがイマイチでスッキリしないことはありますw
ラスボス倒した後のプレイの虚無感に耐えかねて、ポケモン・モンハンができなくなっちゃったんだっけなぁ…(前者は厳選の罪深さに耐えられなくなったのもありますが)
プレイ時間の長短は別にして、俺もゲームの締めとしてのEDは大切だと思う派ですね。Botw、イースⅧ、ゼノブレイド2 …どれもスタッフロールが感傷的なゲームでした。
虚無感ですか・・・それだけの気分になるほど楽しめているってことですね。
ゲームにエンディングが存在すると締まりが出てきて結果的にプレイを続けることが多くあります。
僕もかつてのゲーム観はエンディング=ステータスでした。
やっぱりエンディングを迎えるとお得に感じますよね。
なのでゲーム離れ以前はエンディングの後は二度とそのゲームを遊びませんでしたよ。
しかしゲーム離れ後にFEという何度もやりたいゲームに出会ったのとインディーズやスマホゲーム、運営型タイトルなどここ数年でゲームのあり方の定義が良い意味で打ち砕かれましたので、今のスタイルはおもしろいゲームなら飽きるまでやって、飽きたら2度とやらないか売るなどしてますよ。
でも売った後に買い直すことがザラなので今はDL版を買うことが多くなりました。
一応、今でもゲームプレイではエンディングを目指しますが、最近はエンディング迎えたくない病が寂しさやエンディング演出のめんどくささで発生しちゃうんですよね。
なので今は自分の中で積みゲーの概念は滅亡しました♪ゲームはアーケードスタイルでたまにやろっかなってときにやればいいのです(笑)
ぼくのプレイスタイルだとゲームプレイの締まりが出てくるけど、どうしても使い捨て感が出てしまうのでそこが玉にキズなんですよね(汗)
昔のゲームはアーケードスタイルが大半でクリア出来たらラッキーという認識でした。
それがいつからかストーリー主導になりゲームをクリアすることばかりに目が行くようになってしまいました。
ただ、今流行っているゲームって運営型のソーシャル系や対戦系なんですよね。
こうして考えるとゲームのプレイスタイルも多様化しているなぁって思います。
どんなタイプのゲームが好きかでプレイスタイルは全然変わってきそう。
俺はあまりエンディングにこだわりませんね〜
ダクソ3なんかは長すぎてやっとおわった、、っていう妙な達成感はありましたが!
昔から終わらせるのがもったいなくてエンディングのちょっと前でやめてたりはありましたね
エンディングっつ一つの区切りなのでこだわりはないですが必要とは思います
ダークソウル3はハマりすぎて4日でクリアしてしまいましたw
あのゲーム、長く感じましたか?ぼくは過去2作よりもやや短く感じました。
確かに楽しいゲームだとエンディングを迎えるのが勿体なく感じます。
最近はエンディングがないゲームをしていますが、あれはスポーツゲームと同じで別枠として考えるとして、RPGやADVはエンディングがないと無理ですね。延々と同じ作業が最近は苦痛ですかね。最近は追加シナリオとかありますが、僕は終わったゲームを更に追加でやるのは気持ちが切れて無理です。
最近は時間のかかるゲームが億劫になっていると思います。
エンディングがないRPGもスマホには多いですもんね。
確かに大型ダウンロードコンテンツは配信が遅いと気持ちが途切れてやる気にならないことは多いです。
何らかの区切りは、達成感のために必要ですね。スタッフロールが流れると、そのスタッフから免許をもらえたみたいな満足があります。
同感です。クリア証みたいなものを貰ったような感じですよね!
自分はエンディングの無いゲームも良くプレイしますが、確かにいつも中途半端に終わってしまいますね。途中で止める原因はほとんど新作ゲームで忙しいからですけどね。笑
エンディングのあるゲームでは達成感は大きな要素ですね!特にストーリーが素晴らしいとやり切った感が出るので余韻に浸れます。
気になるゲームが次から次へと発売されるので、エンディングがないゲームはなかなか気持ちよく終われませんよねw
1日がもっと長ければ良いのですが・・・
エンディングを迎えた時の達成感は病み付きになります。なので、ストーリーもキレイに終わると尚更良いですよね!
エンディングっていっても色々ありますからね。
エンディングを終えたら本当に終わりのパターン。
エンディング後に追加要素があるパターン。
エンディング中にゲームがあるパターン等々w
自分はエンディングに特にこだわりはないですが、エンディング中にゲームは個人的にはやめてほしいw ベヨネッタとかそれに当てはまりますがw
エンディングはおトイレタイム・・・じゃなかった、休憩タイムって考えてるんで。
自分がやってるゲームはエンディングが異常に長いのが多いんですよwww
メタルギアは本当にそれw おかげでエンディング中にお休みしたりお菓子食べたりすることが多いのなんのwww 酷い時に入浴した時もまだエンディングが終わってない時も多々w
ゲーム毎にエンディングと定めるポイントが全然違うんですよね。
昔は達成率100%のところがエンディングだったけど、最近は80%辺りのことも増えてきました。
エンディング時のミニゲームですか?
個人的にあの演出は好きなんですよーw
退屈しないし開発者を覚えることも出来ますからね。
確かに最近のゲームはエンディングが長すぎます。
ミニゲームを挿入するタイプは長過ぎないようにしてほしいですね。
エンディングが無いとすっきり別の作品にうつれませんね。頑張ったあげくちゃんとスタッフロールが見れる幸せよ。
マルチエンディングでなくてもいいので、気持ちいいハッピーエンドを準備して欲しいですね。とはいえ悲しさのなかに少しだけ救いのあるビターエンドも好きです。
ヒロインがいる場合は完全に結ばれるわけではなく、これからふたりで歩んでいくのを示唆するのも好きですね。スカイウォードのエンディングはここが良かったです。
ゲームって努力が報われるところが良いんですよね。
現実では頑張っても報われないことって多いですしw
ゲームでバッドエンディングって嫌われやすいけど、達成感と合わせてみると納得です。
スカイウォードソードのエンディングは泣きそうになりました。
お別れのシーンもそうですし、最後の会話も良かったなぁ♪
初めてコメントします。
いつも楽しく拝見しております!
私もエンディングがあるゲームが好きです。理由もほぼ同じです。
スマホゲーは終わりがないものが多く、私は課金をしないので途中で進めなくなりやめるパターンばかりだったので、いまは全くやってません。
私的には追加DLCがあまり好きではありません。さらに楽しめるのはいいのですが、中途半端で発売されてる気がするのと、完全版商法がチラつくからです。どうせ完全版出るだろってことで待っちゃう自分もいます。
共感コメントありがとうございます!
スマホゲー、ぼくもハマったことがあるんですけどね。
辞める時の後味はめちゃくちゃ悪くてあれこそまさに辞職でしたw
追加DLCは100%+αであったら納得します。それでも数年後にはDLC全部入りパッケージが発売されることも多いですが。
エンディングがないとゲームを終えた感じがしないので、エンディングはあった方がいいですね。
気に入ったゲームはエンディングを見た後も引き続きやったりしますし。
でも最近はエンディングよりもトロコンしたかどうかの方が重要になってきてる気も(苦笑)
あぁ・・・ぼくもそんな感じですw
ちょっと頑張れば取れそうなゲームはトロコンを目指したくなりましたよw
閃の軌跡4を最近やっとクリアしましたが、これこそエンディングがなかったら投げて当然なゲームでした。
クリアまで寄り道というかサブ要素を見つけ次第全部やって110時間でした。
サブ要素がほぼ全部時限式なのでやらねばならない使命感に駆られてしまうんですよね。
その後ロックマン11を半日でクリアしました。現在はやっとスパイダーマンをプレイし始めました。
クリアという一区切りがあることでゲームプレイにメリハリが生まれると思うのであまりに重厚長大な作りはそもそもゲームとしてどうなんだろうかと思う今日この頃です。
おお!クリアおめでとうございます!
110時間は長いですね。お疲れ様でした!
一方、ロックマン11は半日でクリアですかw
閃の軌跡4を終えた反動でサクッとクリア出来るゲームを色々プレイするのも良いと思います。
スパイダーマンは完全クリアしても閃の軌跡4の3分の1以下でしょうから、こちらも今のらす2さんからすると気軽な方でしょうね。
ゲームをクリアと言う意味では目印に欲しいな。
クリア後にハードモードプレイアゲインと出されたら生暖かい気持ちで1面挑戦して歯ごたえを感じたらもう良いかと終了するパターンだが。
クリア後のハードモードはなかなかやる気になれませんよね。
そのゲームがアーケードスタイルでめちゃくちゃハマったらダウンウェルのように頑張れますが。
エンディングは何よりもモチベーションに繋がりますね。マルチだけだとあまり長時間プレイできないです。
あとは一応の区切りとして、次のゲームに移るために、あると嬉しいです。なので、マルチメインのタイトルでもシングルモードがほしいですね。
そうそう、エンディングの要素があるだけで心持ちって全然変わるんですよー。
そこまで気合を入れなくても良いのでマルチメインでも最低限のシングルプレイがほしいです!
Kentさんが仰るのはその通りなんですが自分は正反対ですねw
自分は逆にエンディングに近づくと、そのゲームをいつまでも楽しみたい(エンディングは強制的に終わりにさせられる)ため、ラストダンジョン手前でゲームを辞めてしまいますw
そうした方が、エンディングを迎えるよりも長く楽しんでいると感じますからw
まあ、ストーリーゲーの場合は普通にエンディングを迎えることもあるのですが…
逆に、エンドコンテンツ豊富なタイプ(ポケモンみたいな)は早くエンディングを迎えたいと思いますね。ただ、その場合はストーリーにメリハリが生まれるので、ストーリークリアの達成感も味わえるので正にkentさんの仰る恩恵を被れますね。
そうなると…やはりゲームによって考え方が少し変わってしまいますね。
エンディング前で止める人って意外と多いようです。
でも、みなさんの話を聞いて納得しました。
エンディングって別れにも捉えられるので、好きなゲームだと迎えたくなくなるのも無理はありません。
ただ、仰る通り最近はエンドコンテンツが豊富なゲームも増えてきたんですよね。
そういうゲームの場合はエンディングを迎えないとむしろ損だったりします。
その辺はエンディングを迎えないと分からないことなので、事前にクリア後の要素を調べておくと良いかも。
やっぱりエンディングがあったほうが良いですよね。
明確な終わりが存在するゲームが良いですよね。
最初はそれを目指して、エンディングを迎えた時に達成感があります。
そしてエンディングを迎えた後の隠し要素や、一周目を引き継いで二週目などがあれば最高です。
エンディングを迎えると後味が良いゲームがほとんどですが・・・逆にエンディングを迎えると後味が悪いゲームもありますConker’s Bad Fur Dayなど・・・ですが自分はハッピーエンドよりバッドエンドの方が大好きです。
全く同感です。
明確な終わりが存在するからこそ気持ちが引き締まると言うか。
Conker’s Bad Fur Dayのエンディングはタイトル通り後味が悪いですかw
まあ、欧米のゲームはそういうの多いから慣れていますw
そしてConker the Squirrelさんはバッドエンドの方が好きになってしまいましたかw
バッドエンドの3つの魅力があります。
リアリティが感じられる。
バッドエンドの魅力の1つに、ある種のリアリティを感じられることがあると思います。フィクション作品はハッピーエンドが基本だけども、現実ではそう上手くいくとは限りません。
逆に考えれば、悲しみ・苦しみがあるバッドエンドは現実に近いとも言えるでしょう。主人公補正・ご都合主義だけで終わらないのがバッドエンド。
世界観が広がる。
また、「世界観が広がる」のもバッドエンドの魅力じゃないでしょうか?
例えば、ゼルダの伝説で「勇者リンクが魔王ガノンドロフに負けて、世界が滅ぶ」というバッドエンドがあったとします。
これって勇者からすればバッドエンド。だけど、魔王にとってはハッピーエンドですよね? 逆に「勇者リンクが魔王ガノンドロフを倒して、世界を救う」この場合は魔王にとってのバッドエンドとも言えます。
つまり「だれかのハッピーエンドは、だれかのバッドエンドであるかも?」ってこと。普通に主人公のハッピーエンドで終わると、これには気づきにくい。
しかし、バッドエンドになることで作品の中に多様な価値観があると強く示されるわけですよ! これも魅力な気がしますねぇ。
バッドエンドには、最悪という安心感がある。
自分がバッドエンド好きである最大の理由は、これ。バッドエンドになるとある意味で安心するんですよね。
バッドエンドは基本的に最悪の状況でしょう。どうにもならない、どうしようもない状況。主人公が死んでしまうとか一番大切な者を失うとか。
でも、最悪の状況というのは、逆に考えてみれば「それ以上悪くならない」ってことなんです! 「最悪」なんだから、それが1番悪い状況。もう底まで落ちてきている。
それ以上悪くならない、これって安心感あると思いません?
というか、より正確に言えば自分はハッピーエンドの先が不安になるんですよ。物語はそこでハッピーエンド、それはいいですよ? でも、その先はどうなるのやら? 永遠に幸せが続くの? 落ちる可能性だってあるでしょ?
その瞬間はハッピーエンドでも、不幸に転落する可能性はある。でも、すでに最悪の状況まで落ちきってしまえば、それ以上悪くなることはない。
ハッピーエンドの先が不安になってしまう人間としては、すでに底まで落ちきっているバッドエンドには安心感があるんですよねぇ。
ハッピーエンドよりも評価されるのは難しい・・・でも、バッドエンドにも魅力はある! リアリティとか世界観の広がりとか、最悪という安心感とか!
というか、ハッピーエンドの先が不安になってしょうがない。不幸に転落する可能性が・・・ですがバッドエンドだからこそ心に残る作品もたくさんあります。
例えば
「フランダースの犬」
ネロとパトラッシュの死はあまりに悲しい結末「バッドエンド」の一つだと思っています。
でも「フランダースの犬」は名作です。
ネタバレ注意
「Conker’s Bad Fur Day」
最後は周囲にいる面々は、コンカーが内心大嫌いだと思っているこれまでの登場人物ばかり。大金持ちになり、王座を手に入れたことで事実上世界を手に入れたに等しいコンカーは、ここにきてベリーの存在価値がいかに彼にとって大切なものかを知った。王の座など、せいぜい憧れているうちが幸せであり、かけがえのない存在であるベリーを失ったことにくらべれば王などはどうでも良い事だった。
ご都合主義で勝利して、王の座を手に入れ、世界一の金持ちになり、土地でも何でも持ってるが、引き換えに彼女ベリーを失ったことの意味は、コンカーにとって致命的な心の傷である。
本当に大切な物はなんなのか考えさせられます。
そんな自分には、Conker’s Bad Fur Dayはピッタリのゲームです。
質問です。kentworld様
こんなバッドエンド好きな自分をどう思いますか?
「長々と長文失礼しました」
あわわ・・・バッドエンドの魅力を語るためにこんな長文を!?
1つの記事が書ける勢いじゃないですかw
でも、このコメントはゲームのエンディングがバッドエンドで低評価を下す人に読んでもらいたいかも。
そうそう、バッドエンドってリアルなんですよ。
現実ではそう上手く行くとは限りませんもんね。ただ、ご都合主義を求める人も多いのかなと思います。
>こんなバッドエンド好きな自分をどう思いますか?
現実主義なのかなと思います。
でも、コラム記事などを書いていると納得出来るところはありますよ。
特に「だれかのハッピーエンドは、だれかのバッドエンドであるかも?」は「確かに!」って思いました。
物語上の主人公にとってはハッピーエンドだけど全体的を見るとそうとは限りませんもんね。
ぼくが幸せになることも人によってはバッドエンドに感じることもあるでしょう。
バッドエンドの話をすると世の中の深さを感じます。
こんにちは。
私の場合、アクションゲーム。シューティングゲーム等、
運動神経、反射神経、動体視力など駆使しないと
先に進めないゲームはヘタクソなので、
例えエンディングがあったとしても見てないのが多いです(笑)
パズル・アドベンチャー・RPG・シミュレーションなどなら良いんですけどね~
そうでしたか・・・でも、昔の感覚だとクリア出来てラッキーだったんですよね。
今はどんどんストーリー主導になってきたからそうは感じられなくなってきましたが。
お話を聞いているとアクション系は人を選ぶことを痛感します。
アクションゲームは、操作が分かり易くて、
間口が広くて誰でも遊べるんですが、
誰でもクリアできるかというとそうでもないんですよね(笑)
私がスーパーマリオシリーズでクリアできたのは、
GBのマリオランドと、3DSの3Dランドだけなので(笑)
エンディングが見れなくても楽しめれば良いんですよね~
アクションが苦手な方の意見も参考になります。
アクションゲームの場合、どうしてもプレイヤーの実力差が出てしまいますよね。
自分の感覚だけで難易度を語るのは難しいなぁと実感します。
エンディングがあることは1つの安心感になりますね。終わりのないものはやっててつらいです。
エンディングのないゲームであれば、達成率やプレイヤースキルなど進行具合を示すバロメーターが欲しいですね。
そうそう、せめて進行具合を示すパロメーターがほしいです!
そういった目的がどうしてもほしくなります。
エンディングのあるゲームは、最後まで終えたら「クリア」って言いますけど、
オンラインゲームなど、エンディングのないゲームだと、終わる時は「引退」って表現しますよね!
エンディングのないゲームは自分で終わりを見つけないといけないので、そういう表現になってしまうのかもしれませんね、
あぁ、確かに引退はしっくり来ます!
ぼくも終わりがないゲームで辞めることを宣言する時はそのような表現を使うかなー。
後退するのは好きではないのであまり使いたくないんですけどねw
ゲームは言ってしまえばプレイヤー自身が動かしていく一種の演劇なので、エンディングを迎えたときの達成感は感動ものですよね!同時に一つの物語が終わったことへの寂しさも、ゲームだとより強く感じられるんですよね。特に思い入れの強い作品だとしばらく余韻に浸かってしまい、何も手につかなくなってしまうこともよくありましたね。
プレイヤー自身が動かしていく一種の演劇。
なんてステキな表現なのでしょうか♪
プレイヤーが介入出来るからこそ他の媒体よりも寂しさを感じられるんですよね。
この点を上手く活かせば最強の泣きゲーを作れそうです。