
ステージクリア型。ミッションクリア型。
ゲームを紹介する際、僕はこんな表現をよく使用しますが、そうでないゲームとはどんなものなのでしょうか?そして、ゲームプレイにどんな違いをもたらすのでしょうか?
今回はその辺りについて語ってみたいと思います。
ステージ・ミッションクリア型ゲームとシームレス型ゲームの違い

ステージクリア型、ミッションクリア型のゲームは明確な区切りがあります。
ステージをクリアしたら選択画面へ。ミッションをクリアしたら選択画面へ。一方、そうでないゲームは全体がシームレスに繋がっているため、区切りが無いんです。
例えば箱庭アクションゲームの場合、広場のような世界で複数の目的を探す事になるので、ある程度は好きなように攻略が出来ます。
また、複数の箱庭で構成されていたとしてもエントランス的なフィールドで新しいステージを探す楽しさがあります。
一本道のゲームだったとしてもステージクリア画面を表示させず、シームレスに次のステージに切り替わって細切れ感がありません。
これがステージクリア型ゲームの場合、カーソルを移動するだけで他のステージへ行けてしまうんです。
例えば狩りゲーの場合。拠点で支度をしてミッションを受注して、専用のフィールドで目的を達成しに行きます。
目的を達成したら再び拠点へ。新しいミッションが出現するので、再び専用のフィールドへ行く。これのくり返しです。
良く言えば新しいステージ、ミッションを探す手間が省けるので楽ですが、悪く言えばブツ切り感があり、キャラクターを動かして楽しむゲームの場合、冒険している感が薄れてしまいます。
僕は冒険している感を重視しているので、ブツ切り感は苦手です。
なので、できるだけ区切りの無いシームレスプレイを実現してもらいたいんですよね。繋ぎ目があるのとないのでは想像以上に没入感が変わって来ます。
再びトレンドになってきたステージ・ミッションクリア型ゲーム

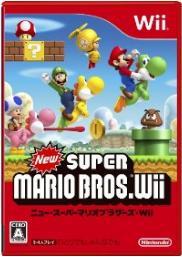
日本でのトレンドはどんどんステージ・ミッションクリア型ゲームにシフトしています。
みなさんに話を聞いてみますと、箱庭アクションで次の目的を探している時間が無駄。休憩できる時間が欲しいとのこと。
かつてはステージ・ミッションクリア型ゲームは時代遅れと言われ、シームレスプレイを重視する方へシフトしていたのに、「モンスターハンター」や「Newスーパーマリオブラザーズ」が流行り、スマホゲームが主流になってからは再び進行形式のトレンドが変化してきています。
僕は頭が古いのか、今でもステージ・ミッションクリア型ゲームは旧世代的なものに感じているんですけどね。
スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS – 3DS
売り上げランキング: 36
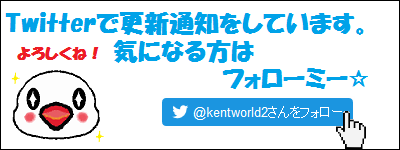


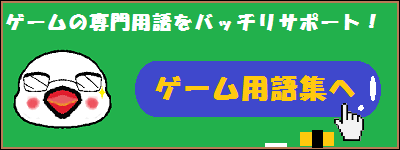
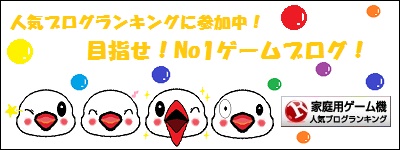
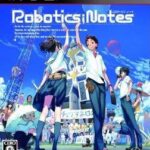
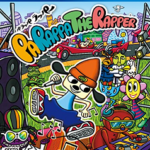







どちらがいいかはゲームジャンルによるなぁ。
移動時間が面白くないのであれば選択型の方が無駄がなくていいです。
モンハンみたいにオンとオフ分かれてるゲームならなおさらですね。
モンハンは個々のマップのシームレス化は望みますが完全オープンは否定派です。
マリオギャラクシーも拠点マップはダルい印象強かったから2の形式の方が好きだし、
MGSVもミッション開始位置に移動しなきゃいけないのがダルかったしね。
ミッション中はシームレスの方が当然いいですが。
DQHも2のフィールドの作り込みレベルならば1の形式が良かった。
緩急つけてオンの時に没入感得られると感じてます。
一方でRPGやアクションADVなんかは冒険してる感じ欲しいからそっちの方がいいですね。
分かりやすい例では仁王よりはソウルシリーズの方がいいw
ファストトラベルの使い勝手や移動中の作り込みの労力が大変ですがね。
シームレスを望むばかりにロードが長くなるなら結果的に没入感切れるからそこの兼ね合いも大事かな。
ステージクリア型ゲームの良さは、快適性ですもんね。
この快適性の高さをオープンワールド型ゲームでも上手く取り入れるのが理想的かなぁ。
ファストトラベルの機能を上手く拡張してやってほしいですね。
あとはロード時間が課題になりそうか。
同意ですな。
純粋にアクションを楽しみたい作品や、流行ってるからただ単にオープンワールドとかシームレスにしてみましたみたいな作品だと、ステージクリア型の方がいいですね。
ブラッドボーンとか、ゼルダの伝説とか、ホラーゲームみたいな世界観含めて楽しみたい作品だとシームレスの方が好きです。
仁王も、ステージクリア型でぶつ切りのように感じてしまってそこが少し残念だったので。
その代わり仁王はロードがびっくりするくらい早かったので一概にシームレスこそ至高とは言えないですが。
なんか同じ感想だからか同じようなこと書いてしまったw
私はステージクリア型とシームレス型はあまり強く意識したことがないのでどれが古いかどうかは考えたことがないです。それぞれメリットやデメリットがありますが、私は空いた時間にゲームをするのがどっちかというと好きな人なのでステージクリア型派ですね。シームレス型はそのゲームに入り込める没入感があり、その点ではゼルブレなどのゲームが最高に楽しいです。しかしその分、時間泥棒な作りになってしまいがちなので空いた時間に気軽にとはいかなくなるのでそこが難点です。ステージクリア型はおっしゃる通り、ずっとやるには辛く飽きやすいですが、時間が空いたときにちょっとやろっかなという分にはとても入り込みやすいです。スマホゲーはそこをうまく狙いましたよね。ステージクリア型はライト層が好むイメージがありますね。
私はステージクリア型がどちらかというと遊ぶハードルが低くて嬉しいですが、そればっかりなのもゲームが飽きっぽくなるのでゼルブレやトワプリなどのシームレス型も嫌いではありません。こういうのも共存していけたらいいなと思ってます(^∇^)
ステージクリア型は昔のトレンドだったので、僕はどうしても旧世代的に感じてしまうんですよね。
今のユーザーだったら古さを感じないのも無理は無いと思います。
僕はゲームに没頭したいと思ってしまうので、
ステージに区切りがあると邪魔に感じてしまうんですよねぇ。
ステージ制の方が、どこまでプレイしたのかが解り易いってのもあるのかな
あと、オープンワールドは移動が面倒ってのはシミジミ思います。
ゲームをガッツリやる暇が無い場合(1日30分~1時間程度しかゲームの時間がとれない場合)は移動で時間のくうゲームって中々やる気にならんのです。
大概、それだけしかゲーム時間がとれない場合は、そういうゲームは起動すらしませんですね
移動が楽しいと言われても、目的地についたら本日のゲーム時間終了→数日後ゲーム再起動→あれ?俺なんで此処に居るんだっけ?という状況が多々あります(笑)
オープンワールドはオープンワールドで良いところもあるんですが、ステージクリア型も気分が変わって良いですし、区切りがわかりやすいです。
結局ゲームのコンセプトや世界観にシステムが合ってればいいのかな、タイタンフォール2もステージ制だったけど古さは感じなかったし
ステージクリア型ゲームの方がライトユーザー受けは良いと思います。
色々とスポイルしていて分かりやすいですからね。
タイタンフォール2の場合はステージクリア型でしたが、
区切りが少ないのであまり気になりませんでした。
ステージクリア型でもどこまで細切れになっているのかで印象は変わってきますね。
ミッションクリア型がトレンドになってきた原因は、僕の考えでは、
①忙しいときでも、サクッとできるスマホゲーの台頭
②オープンワールドのシームレスによる自由からの逃走
だと思います。
①については、パズドラブームから始まりました。これにより、忙しくても簡単にできるゲームが好まれるようになりました。そこで形式として最も合っているのが、ミッションクリア型だったんです。
②は人間の性です。自由は制限がない分気楽ですが、楽しみ方を全て自分で考えなければなりません。しかも最近のシームレス型はオープンワールドになっていて、すごく広いです。そうなると、時間がかかり、それがストレスになってしまいます。なので、ユーザーはそれから逃れるため、簡単にできるミッションクリア型に流れていったんだと思います。
以上、C-rexの『論理と推理の実験劇場』でした?。
こうして考えるとステージクリア型ゲームは日本人の国民性に当てはまっているんでしょうね。
シームレス型ゲーム好きとしては、理解は出来るけど、納得は出来ないのが僕の正直な気持ちです。
単にスマホゲーはステージクリア形で作りやすいでしょう
ある程度にプレイヤーを早くクリアできないように、スタミナ制になってます
スマホゲーの次のブームはスタミナ制を無くし、プレイする楽しさも運営側も長期運営の利益を保つ新しいシステムが出るまでだと思います
狩ゲーはモンスターを倒す行為に特化するジャンルです
マップをシームレスになって、探索要素も増えると、死にゲーというジャンルが出てきます
狩ゲーはシームレス化する完成形は死にゲーに近いだろうと思います
同じモンスターが数十回も戦ったら、流石にネコ車とかワープする手段がないと文句が出ますw
SRPGも一応ステージクリア制だから、無くなるとつらいです
スタミナ制との相性もありますね。
最近はだんだん、スタミナ制を取り入れなくなるスマホゲームが増えてきたので、
それで進行形式のトレンドが変わったりしないかな?
シミュレーションRPGもステージクリア型ですが、ファイアーエムブレム最新作は少し違いました。
最近の大作はRPG、アクション、アドベンチャー、レース、シューティング等色々なジャンルを包括してますからシームレスじゃないと破綻しちゃいますね
一つのジャンルに特化したゲームならステージ式でいいです
スマホは電池的な問題でスリープモードが厳しそうですし外で没入しても危険ですのでシームレスなゲームは無理なんじゃないですかね
トレンドではなくハードの限界かと思います
モンハンは大作なのでいい加減にシームレス化してほしいですね、次は3DSじゃないはずなのでマップ選択式(箱庭)になってると思いたい
色んなジャンルの要素を盛り込んでいるからこそのシームレス。それはありますね。
スマホは性能上がっていますが、汎用機である以上、制約はまだまだ多そうですね。
色々作れそうで難しいのかも。
モンハンの次回作は楽しみです。そろそろ、大きな進化を迎える時が来ましたからね。
個人的にも基本的にはシームレス型のゲームの方が好きですね。
オープンワールド好きで探索好きなので、マップがシームレスに広がっているとワクワクします。またシームレスにする事によって没入感が増し冒険している感も出るので、一本道でも出来るだけシームレスだと嬉しいです。
しかしジャンルによってはステージクリア型の方が良いなと思う事もあります。特に高難易度ARPGいわゆる死にゲーはステージクリア型の方が良いです。ボスとは何戦も戦ってとても疲れるので一区切り入れてもらえるのはありがたいし、ロードも短くなるので死んだ時のストレスが大幅に軽減されるのでその方が嬉しいです。
シームレスだからこそのワクワク感!これは、色んなゲームで感じています。
高難易度アクションRPGでもそうですね。
一区切りに関しては、篝火が役立っています。
ダークソウルやブラッドボーンではレベルアップが出来たり、旅仕度も出来たので。
でも、仁王はステージクリア型だからこそロード時間が早くなったので、メリットも感じられました。
個人的にはステージクリア型が好きですね。自分がどこまでやれているのか、進行度はどれくらいか、などということを実感しながらやれるのでプランが立てやすいというところです。今日はどこまでやろうか、きりのいい所までやって休憩することで飽きずに楽しめますから。集中力が途切れない自信があるならシームレスの方が良いのではないかと。
RPGはシームレスでもいいですね。ストーリーの部分で区切りが見えやすいので。
プランが立てやすいというのはありますね。
プレイ日記を書く時はそう感じることがありますので。
休憩に関してもステージクリア型の方が取りやすいですね。
街毛さんのプレイスタイルにはよく合っていると思います。
スマホゲーが強くモンハンが売れ続けている日本では、ステージクリア型が好きな人が多いかもしれません。
でも、やっぱりシームレスの方が好きです。
単純に、どこまでも移動できるのがいいのもありますが、目的地に行く途中に寄り道ができるのが楽しいから、というのが一番大きいですね。逆に言うと、その点でステージクリア型は物足りなく感じます。
僕も同じような感じです。
少数派かもしれませんが、シームレスの方がワクワクするし、楽しいと感じることが多いんですよね。
ステージクリア型はお手軽だけど、スポイルしているところがあるので、それが物足りなさに繋がっているというのはあります。
ガチガチのアクションだったらステージ制のほうがすきですね。逆にアクションRPGだったらシームレスのほうが好きです。
前者は好きなとこの高難易度がプレイしやすいですし後者は冒険してる感があって良いです。
ミッションクリア型だったらリザルトが凝ってたりsランク以上でご褒美だったりすると楽しいです
ご意見、ありがとうございます。
ジャンルごとに合う合わないはありますよね。
僕は不便だと分かっていてもキャラクターを動かすゲーム全般でシームレスを求めてしまうところがありますがw
スコアアタックやタイムアタックがあるゲームだったらクリア型の方がいいと思っています。(レースゲームだけ例外)
でも、シームレスだからこその良さってありますからね。
どっちがいいかっていうより、どっちがそのゲームに合うかって考えていますね。
でも個人的にはシームレスの方が好きですかね。
ステージクリア型のゲームもよくやってるんですけど、長く遊んでるのはどちらかというとシームレスの方ですね。
あ、クラッシュは例外ですw
シームレス型だと安っぽさを感じないんですよね。
スコアアタックやタイムアタックがあるゲームですか?
シームレス型のゲームでもファストトラベルの機能を拡張して
スコアアタックやタイムアタックを瞬時に出来るよう、作ってくれたら良いんだけどなぁ。
プレステとかだと、最近はジャンプが一回しか出来ず低空までしか飛べないゲームも多い気がします。アトリエやLEGOなどがそうですね。爽快に跳んでみたいものです。
二段ジャンプですか?僕がプレイしているゲームはむしろ、二段ジャンプ出来る作品が目立っているかなぁ。
僕が遊んでる範囲では一回しか跳べないのばかりです。Newゴルフも一回しか跳べなさそうです。kentさんが遊んでるゲームの内リアル調な奴にそういうの多いのかな?
LEGO、アトリエ、ブルリフと皆一回しか跳べません(笑)
例えばユーカレイリー、ニーアオートマタは二段ジャンプ出来ましたよ~。
なので、コメントを読んで意外に感じました。