
今回から新企画として特定のゲームメーカーにスポットを当てた振り返り記事を書いていきたいと思います。
第一弾はハドソンです。「ボンバーマン」、「桃太郎電鉄」などの人気シリーズを生み出したメーカーとして知られるハドソンを個人的な観点で語って行きます。
目次
1980年代前半:任天堂初のサードパーティ

ハドソンは元々、パソコンのソフトメーカーでした。そのため当時としては技術力が高く、任天堂とは「ファミリーベーシック」というファミコン向けの周辺機器を作っていたようです。
これがきっかけでハドソンはファミコンソフトの開発を開始。数多くの大ヒットタイトルを生み出します。
まず、誕生したのが「ロードランナー」。アメリカで展開されたアクションパズルゲームの移植作ですが、100万本を超えるミリオンセラーとなりました。
「忍者ハットリくん」、「ドラえもん」といったキャラクターゲームのヒットも印象的です。
特に「忍者ハットリくん」は150万本を超える大ヒットとなり、1998年のGB「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」まではずーっとキャラクターゲーム最大のヒット作として記録に残っていました。今では信じられない話ですね。
1980年代中盤:高橋名人が大ブレイク!

1980年代中盤、ハドソンの広報が思わぬ人気になります。それが今でも知名度が高い高橋名人です。
「ゲームは1日1時間」という名言を生み出し、1秒間に16回押す16連射が強烈で、当時の子供たちから絶大な支持を集めていました。
僕も高橋名人には憧れていましたね。名人のようにゲームが上手くなりたい!ファミコンソフトをプレイしながらそう思っていたものです。
名人が主人公の「高橋名人の冒険島」も1作目は100万本を超える大ヒットとなりました。当時の作品らしく難易度は高かったけど、個人的には「スーパーマリオブラザーズ」と並ぶほど好きな2Dアクションゲームでしたね。
ただ、名言の「ゲームは1日1時間」には当時、苦しめられました。
この名言が生まれてしまったために家庭内で「ゲームは1日1時間」のルールが生まれたもんだから家でゲームをプレイする時は親にストップウォッチでプレイ時間を計測され、1時間経ったら強制的に電源を切られてしまいましたから・・・。
「高橋名人の冒険島」は大ハマリしましたが、名言の「ゲームは1日1時間」は嫌いでした。

ちなみに高橋名人とは実際に会った事があります。子供の頃から憧れだった高橋名人に会えた時は嬉しかったなぁ。過去にタイムスリップして子供の頃の自分に会えた事を伝えたらどんな反応をするんだろう?
1980年代後半:PCエンジンの誕生


1987年、ハドソンは日本電気ホームエレクトロニクスと共同開発して新型ゲーム機、PCエンジンを生み出しました。
PCエンジンはファミコンよりも遥かに性能が高く、一世代進んだ高性能ゲーム機で少し上の層を中心に人気を獲得。ファミコンでは実現不可能な高い表現力の作品が数多く生まれました。
特に有名なのが1992年に発売された大作RPG、「天外魔境II 卍MARU」です。SUPER CD-ROM2というPCエンジンの周辺機器が必要でしたが、プレイしたユーザーの間では評価が高く、50万本前後の大ヒットを記録。
その人気は今も根強く、ユーザーが選ぶ歴代ゲームランキングではそれなりに高い位置にランクインしています。
このようにPCエンジンは一定の支持を得ることに成功しましたが、興味深いのが、ハドソンは本ハード発売以降もファミコンにソフト供給をしていた事です。
ファミコンを踏み台にしてPCエンジン市場を生み出したのではなく、共存の道を歩んだんですね。
当時としては技術力が高かったハドソンはファミコンでのソフト開発だけでは物足りなかったようで、独自に日本電気ホームエレクトロニクスと高性能ゲーム機を共同開発してそちらでも好きなように作っていたようです。
1990年代前半:スーパーファミコンでもヒット作を連発!
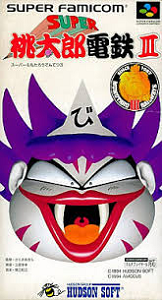
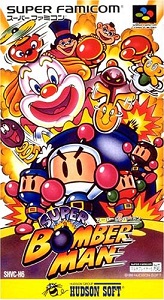
時は流れて1990年代前半、ハドソンはこの頃も元気でした。
「ドラゴンクエスト」人気に便乗して生まれたRPGの「桃太郎伝説」は派生作品の「桃太郎電鉄」が思わぬ人気になり、シリーズ初のスーパーファミコンソフトとなった「スーパー桃太郎電鉄III」は100万本を販売。
1980年代からシリーズが続いていた「ボンバーマン」は1990年に発売されたゲームボーイ版、PCエンジン版で対戦プレイが可能になり、年に2~3作は発売される定番タイトルになりました。
どちらも対戦プレイが面白いので、当時は家に友達を集まったら「桃太郎電鉄」や「ボンバーマン」シリーズを遊ぶのが定着していたもんです。熱くなりすぎて友情崩壊しかけた事もありましたが、それも今となっては良い思い出。

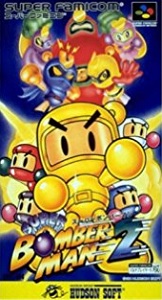
余談ですが、「ボンバーマン」から派生して「ビーダマン」というホビーが1990年代中盤に生まれました。
人形にビー玉を詰め込んで発射する遊びを発展させたホビーですが、独自にシリーズを重ねていき、特に「スーパービーダマン」シリーズは月刊コロコロコミックとのタイアップによってミニ四駆やハイパーヨーヨー、ポケモンカードゲームと並ぶ人気を獲得。
販売や開発はタカラトミーになりますが、こんなところでもハドソンのコンテンツが人気を見せていたんですね。
1990年代後半:3D化の流れに乗れず、第一線から後退

1994年、PCエンジンの後継機となるPC-FXが発売されました。しかし、前ハードのPCエンジンとは異なり、販売台数は大苦戦。
大きな要因として挙げられるのがキラータイトルの不足に加え、当時のトレンドだった3Dポリゴン機能を搭載していなかった事です。
同世代期のプレイステーションは「リッジレーサー」や「鉄拳」で。セガサターンは「バーチャファイター」で。N64は「スーパーマリオ64」で派手な3Dゲームを展開しており、2Dゲームは時代遅れと見られていたので大多数のユーザーにPC-FXは地味に映ってしまったんですね。
僕も当時は3Dゲームに目が行ってしまい、2Dなだけで興味を失っていたもんです。
本ハードを最後にハドソンはハード開発から撤退。サードパーティに戻る事になり、1996年にセガサターンへ。1997年にプレイステーションやN64に参入を果たす訳ですが、時既に遅し。
PC-FXの開発に費やした2~3年のタイムロスは大きく、最先端となる3Dゲームを作る事はなかなか出来ませんでした。
当時発売されたファミ通のクロスレビューを見てもハドソンのゲームで高評価な事は少なくなっていましたからね。
僕は1980年代のハドソンを知っていたので、クロスレビューの低評価を見て「あれ?ハドソンってこんな凡作を生み出すメーカーだったっけ?」と思ったものです。
同時期、メインバンクだった北海道拓殖銀行の破綻により資金繰りが悪化。ハドソンの経営状況はますます悪くなっていきます。
2000年代前半:マリオパーティで首の皮が繋がる

2000年代前半、この頃になると「桃太郎電鉄」シリーズなどごく一部のヒット作しか生み出せなくなりました。
同じく看板タイトルだった「ボンバーマン」は2000年辺りから人気が低下。知名度とは裏腹にヒット作は生まれなくなりました。
そんなハドソンを支えていたのが開発を担当していた「マリオパーティ」シリーズです。本シリーズは毎年発売され、「桃太郎電鉄」シリーズ以上の人気を獲得していました。
任天堂との付き合いはこの時点で20年以上になりますが、ますます絆が深まるばかりですね。
余談ですが、ハドソンはファミコンやN64で最後にゲームソフトを発売したメーカーでもあります。この事からも任天堂との関係の厚さを感じさせますね。
関連記事:各ゲームハードで最後に出たゲームソフト
2000年代後半:Wii人気に便乗!
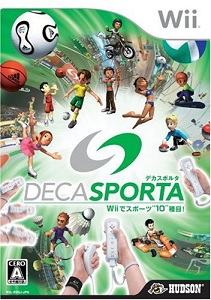
2000年代後半、ハドソンから大ヒットタイトルが生まれます。
それがWii「DECA SPORTA Wiiでスポーツ”10″種目!」。まるで「Wii Sports」の続編かのように見える本作は国内で22万本。全世界で277万本を記録する大ヒットとなり、ハドソンの経営危機を支えました。
それ以外にもハドソンはWiiで「めざせ!!釣りマスター」、「カラオケJOYSOUND Wii」、「桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合!の巻」などをヒットさせる事に成功。
Wii市場に馴染めないサードパーティが多くいたなか、比較的上手くやっていました。
しかし、それも長くは続かず、「DECA SPORTA」はユーザー評価の低さによって2作目以降は売上激減。それ以外の作品も「桃太郎電鉄」を除くと一発屋に終わってしまいました。
2010年代前半:ハドソンブランドの終焉へ

ハドソンは2005年からコナミの子会社となっていました。この頃から社風が変化していたようで、徐々に主要人物が退社。
2011年にはついに高橋名人もハドソンを退社してしまいました。同時期には「桃太郎電鉄」シリーズのさくまあきらさんも決別。
頼みの綱だった「マリオパーティ」シリーズも主要メンバーがエヌディキューブへと移籍し、開発はそちらが担当する事になりました。
2012年にはコナミデジタルエンタテインメントに吸収合併する形で法人としてのハドソンが消滅。もう、新作ゲームであのハチ助ロゴを見る事は出来なくなりました。
コナミがハドソンブランドを有効に活用してくれたらまだ良かったんですが、当時からソーシャルゲームへの注力が始まり、コンシューマー向けにはほとんど新作を発売しなくなります。
このままハドソンは消えてしまうのか?誰もがそう思っていた中、奇跡が起きます。
2010年代後半:看板タイトルが復活!
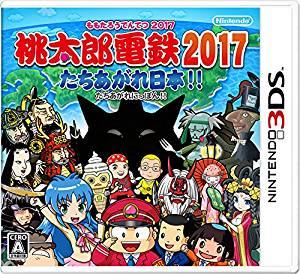
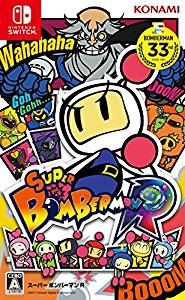
多くのユーザーからハドソンの名前が消えていた2016年。ニンテンドー3DS向けに「桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!!」が任天堂から発売される事になりました。
任天堂がコナミにライセンスを支払い、「桃太郎電鉄」シリーズのスタッフが在籍しているヴァルハラゲームスタジオが開発を担当するという形で奇跡的な復活を遂げたんですね。
久しぶりに発売された事もあって本作は30万本近いヒットを記録。存在感を見せつけました。
さらに、2017年にはニンテンドースイッチで「スーパーボンバーマン R」がコナミから発売。
こちらは久しぶりの新作による待望感に加え、ハードコンセプトとの相性の良さで全世界で50万本以上の大ヒットを記録。
サードパーティのニンテンドースイッチ向けタイトルとしては最も成功した例に挙げられるほどの結果を残しました。
どちらもユーザー評価は低めですが、ハドソンは子供の頃からお世話になっている思い入れのあるメーカーなので、こうしてまた元気な姿を見せてくれたのは嬉しいですね。
全体のまとめ

振り返ってみるとハドソンは任天堂との関係が熱く、親友のような仲ですね。ハドソンがいなかったら任天堂のサードパーティ市場も大きく変わってきたと思います。
残念ながらハドソンは今もコナミの手の中なので全盛期のような活躍はもう不可能だとは思いますが、「桃太郎電鉄」や「ボンバーマン」シリーズの面白さは永遠に不滅で、今後も何らかの形で生き続けてくれると嬉しいです。
▼ゲームメーカーヒストリー記事一覧
ハドソン / スクウェア / エニックス / レベルファイブ / カプコン
売り上げランキング: 209
売り上げランキング: 503
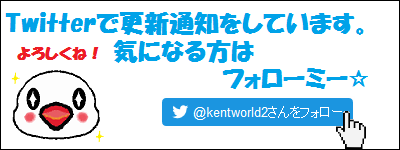
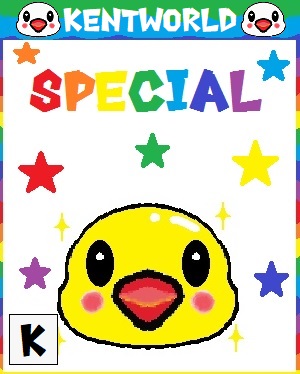


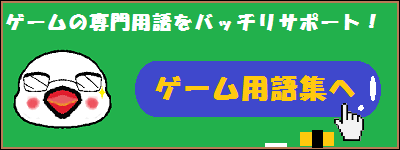
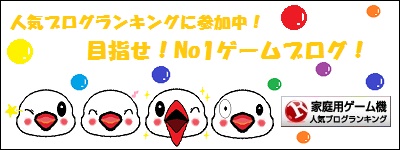
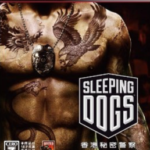







ロードランナーはYouTubeでプレイ映像を何度か観ました。あと、続編のアーケードゲームが街中のゲームセンターにあった記憶があります。
高橋名人は先日、「しくじり先生」に出てましたね、それを受けてのこの記事ですね?ちなみに、僕は名人と出身地は近いですね。まぁ、区は遠いですけどw
ロードランナーは一斉を風靡したんですよね。
最近はご無沙汰していますが・・・
そうそう、高橋名人は最近、しくじり先生に出ていました。
以前からハドソン特集はしようと思っていたので、このタイミングで公開してみたんです。
ハドソンと言えば北海道のゲームメーカーですもんねw
テレビ朝日系バラエティー番組
「しくじり先生」
にあの高橋名人が出演&講義!!
私も見てました!
内容はもう覚えていませんが、なにやら“詐欺”まがいだったことを告白したとかなんとか・・・?!いや犯罪としての「詐欺」ではないのは明白ですが!面白おかしく講義するための“詐欺”発言だったかと・・・あれ?!
なお高橋名人の「デマ」情報については私は当時コロコロコミック連載中だった漫画(「ファミコン少年団」だっけ?)で知りました!!
しくじり先生!面白かったですね~!
個人的には時効ネタと言うか「高橋名人も大変だなー」と温かい目で見ていましたw
その実態はハドソンの一社員ですからね~。会社の“方針”には逆らえなかったとか?!
高橋名人といえば、テレビ番組では女性声優の日高のり子(ひだかのりこ)さんと共演したり、映画では女優の鈴木保奈美(すずきほなみ)さんとも共演していたんだよな~!さらに歌手としてもメジャーデビュー!ファミコン名人の枠を大きく超えた存在でしたね!!
でもハドソンの一社員というのは変わらなかったんだよな。
高橋名人ほど不思議なゲーム人生を歩んだ人は居ないのではないでしょうか?
一般層の間では未だにゲーム関連ではトップクラスの知名度かも!?
いやー釣りマスターは小学生の時めちゃくちゃやりました笑。
ぜひ今こそ釣りゲーが出て欲しいですね。
釣りマスターをプレイされていましたか!?
最近は釣りゲームがスッカリ発売されなくなりました。
これは面白いです。面白いですよ。
読みやすさと起承転結がしっかりしていて、丁寧な文章が持ち味のkentさんと相性ばっちりです。
正直言うと、最近のコラム記事は一発ネタ感が強くて読みごたえが足りないと感じることが多かったので、シリーズ化してくれるのは嬉しいです。
ハドソンといえば、バイハドソン♪の起動音が一番に思い浮かびます。
自分は64、PS世代なのでハドソンといえばボンバーマンと桃鉄のイメージしかありません。全盛期は少し前だったんですね。
どちらのゲームにも言えることですが、ふと無性に遊びたくなるタイトルなんですよ。
定番タイトルという言葉がピッタリです。
PS2~PS3時代に多くのソフトメーカーが離れていったと聞いたことはありますが、2D→3Dへの移行時期にも遠ざかっていくことがあったんですね。
ありがとうございます!
僕は漫画を描いていた過去があるので、
過去の出来事を組み合わせてストーリーを作るのが好きなんですよねw
コラム記事はすみません!今回の記事ほど規模が大きい内容のものはなかなかコンスタントに書くことが出来ず、
繋ぎとしてその場しのぎみたいなものも定期的に公開させてもらっています。更新頻度を落としたら良いんですけどね。
自分が書けそうなゲームメーカーヒストリーは20社以上あるので、今後も期待していてください!
ハドソンは1980年代~1990年代前半までのメーカーでしたねぇ。
それ以降は3Dの流れに乗り切れず、大手ゲームメーカーではなくなってしまいました。
PS3に至ってはダウンロードゲームしか発売できませんでしたからね(^_^;)
高橋名人の冒険島!本当に小さな頃ですが、いとこのお兄ちゃんがやってるのを見てました。
あの音、もう忘れられないですね!ご本人と2ショットはすごい♬
ハドソンはボンバーマンが可愛いくらいであまり馴染みがなかったのですが、桃鉄クリエイターさくまさんがコナミから半ば追い出されたような形というのは聞いていたので悲しい気持ちになったものでしたが、そんな形で救済されていたとは!
ベヨネッタやゼノクロといい近年の任天堂はこういう仲裁役が上手ですね。
今は和サードはなかなか元気が出ないと思うので、どうにかいろんな場所で協力しあって存続して欲しいな。
ボンバーマンにはちょっと惹かれます。
高橋名人の冒険島、ご存知でしたか!
1990年代前半までは人気のシリーズだったんですよね。
僕も幼年期にファミコンのIIIをよくやっていて、大ハマリしていました。
なので、本人とのツーショットは念願でしたね~。
仰る通り、最近の任天堂は人気シリーズを救済する事が多く、
その辺りはさすが最大手のゲームメーカーだなぁと思います。
まだまだ眠っている人気シリーズは数多くあるので、助けてやってほしいです!
新桃太郎伝説はスーファミのRPGの中ではトップクラスに面白かったです。
これもSwitchで新作かリメイクを出したらひょっとしたらこの前のボンバーマン位は売れるかもw
無理に3Dにしなくても2Dで良いから作って欲しいです。
桃鉄やボンバーマンはパーティーゲームの定番でしたね。
基本的にゲームは一人プレイを好む自分ですが、ワイワイ騒ぎながら楽しく遊んでいました。
桃太郎伝説シリーズはご無沙汰ですよね。
電鉄シリーズばかりが目立っているけど、
こちらが本編なだけに復活しても良いと思います。
昔懐かしの2Dグラフィックのほうが良いでしょうね。
ハドソンは多数のパーティゲームを生み出しました。
今でも主要スタッフがハドソンブランド以外でパーティゲームを生み出していて、密かに活躍していますね。
第一弾はまさかのハドソンですか!
桃鉄とボンバーマンしか知らないんですよね(^_^;)
高橋名人の存在は知ってますが。
「ゲームは1日1時間」って子供にとっては大事だと思うよ。
自分もそうでしたが当時は物足りなかったけどあの制限は今となってはとても良かったと思ってます。
友人と遊ぶ時だけは特別だったりしてくれましたしね。
子供は優先順位とかつけられないし本当に勉強しなくなると思うしね。
絶対kentさん夜更かししまくりのダメな子になってそうw
特にゲーム黎明期だから余計に反発強いから中々いいキャッチフレーズだと思うな。
これないと全面禁止にされる家庭絶対増えたと思う。
PCエンジンってハドソンだったのかー知らなかった。
ハードメーカーって昔は多かったんですね。
ハドソンブランドは比較的ライトよりなものも多いし今となっては貴重ですよね。
桃鉄とボンバーマンは今後どうなるかわかりませんが任天堂と組んででも続いて欲しいブランドです。
次はちゃんと評価される作品にしてね!w
最近、ハドソンを思い出す事が多いので、第一弾にしてみました。
次回はウユニさんが大好きなメーカーをチョイスしたいと思いますw
昔はもっと人気タイトルがあった印象なんですが、
今となっては桃鉄とボンバーマンしか残っていませんね・・・
「ゲームは1日1時間」がなかったら僕はもっとダメな子になっていたかもしれませんね。
昔はゲームの制限時間が厳しく、あまり長時間プレイ出来ませんでした。
おかげで1本のゲームをクリアするのに1ヵ月かかったなぁ。
PCエンジンは少し複雑で、発売元は日本電気ホームエレクトロニクスですが、
ハドソンはファーストパーティとして牽引していたんですよ。
なので、実質、ハドソンのゲーム機だと思っています。
ハドソンはパーティゲームの開発を得意としていますからね。
主要スタッフはWii Partyやバトルスポーツ めく~るも開発していますし、
ハドソンの遺伝子は今もパーティゲーム市場を支えていると思います。
>次回はウユニさんが大好きなメーカーをチョイスしたいと思いますw
スク○ニやな?w
歴史語るには大ボリューム待ったなし!笑
確かに子供の頃はクリアに1ヶ月どころか2,3ヶ月以上かかるのもザラだったけど、
だからこそ脳裏に強烈に焼き付いてるというのもありますね。
SFCのドラクエとか未だに宝箱の場所や中身までかなり覚えてる自信ありますよw
ゲームできないから攻略本読んで楽しんだりもしてたなー懐かしい。
次回のゲームメーカーヒストリーは今回の記事が可愛いくらいの大ボリュームになるかもしれません。
だからこそ書き甲斐があり、反響も凄そうなので、ゲーム情報が少ない日の起爆剤にしたいと思います。
長期間に渡ってクリアしたからこそ思い出に残るというのはありますね。
次回はウユニさんが昔、プレイしたゲームの思い出にいっぱい触れることになるかもしれません。
ちょうど先日の「しくじり先生」に高橋名人が出ていただけに、すごくタイムリーな記事ですね。
ハドソンと言えば桃鉄、ボンバーマンと並んで思い出すのがスターソルジャーなどのシューティングですね。本当に今プレイしても熱くなれる名作揃いです。
個人的に一番好きなのは迷宮組曲です。
リメイクとかされないかなあ………
「迷宮組曲」には続編がありました!
「ドレミファンタジーミロンのドキドキ大冒険」
「THIS IS THE END OF EPISODE 1 SEE YOU AGAIN!」
ファミコン版「迷宮組曲」を8周クリアした時に出る隠しメッセ-ジ(!)ですが、この時、「2」を出す気があったのか、
『EPISODE1』と表記されてましたが、実際に「迷宮組曲」の2作目が登場したのは10年後の1996年、ハードはファミコンの後継者だったスーパーファミコンでした。
スーファミ末期に突如何の前触れも無く現れた続編ですが、もともとファンタジーっぽかった世界観が、絵本のレベルにまでなって帰ってきました。(ワクワク!)
実際に、ゲームも「迷宮組曲」とは全く違う内容で(え?!)、シャボン玉で戦うステージクリアタイプのアクションゲームと化していました。
・・・ってこれは“リメイク”と呼べるような作品じゃないですね(汗)。ぬか喜びさせてたらすみません。(映像を見かけていざ調べてみた私自身もがっかりしてます)
確かにこのタイミングでハドソン特集は絶好のタイミングでした!
スターソルジャー、あったなぁ。昔は2Dシューティングの名作が色々出ましたよね。
桃鉄とボンバーマンしか残っていないのは惜しく感じます。
ハドソンといえば、やはり「桃太郎電鉄」かなぁ。
ゲームボーイの2を、公園でよくプレイしていました。
あと、ファミコンのドラえもんも、印象に残っています。
ここでもゲームボーイ!
マージさん=ゲームボーイの方程式が出来上がりそうです。
ドラえもんのゲームはエポック社のしかプレイしていませんでしたが、
ハドソン製のは評判が良いですね。
ハドソンって言ったら桃伝と桃電ですね。
なんか、凄く懐かしい気分になりました。
まだソフトはあるというのに・・・w
高橋名人と言ったらボタン連打ですね。
自分は一応自己最高は10秒間で137回(6年前)ですね。
ただ、記憶にしかないので今やるともうちょっと落ちてそうです。
ハドソンと言ったら過去のイメージが強いですもんね。
僕も振り返ってみて懐かしくなってきました。
って連射速度早い!?
6年前のようですが、今の高橋名人と互角なんじゃないでしょうか!?
ハドソンはロードランナーからお世話になってました。記憶ではスターソルジャーの時くらいに高橋名人が16連射でボタンにバネを仕込んでいてインチキして逮捕されたぞ‼って学校で噂になってましたね。
PCエンジンの頃は世間がバブルで僕も小金持ちだったので、PCエンジンをフルカスタムしていました。ハドソンの天外魔境シリーズは感動しましたよ。
その後は全く関わりがなくなりましたね、拓殖銀行の破綻で話題になったくらいかなあと思います。
振り返ると子供の頃からお世話になっていますが、なくなると寂しいですね。
kiyoppyさんはハドソンと深く関わっていたようですね。
PCエンジンの話が出ていたので、そんな気はしていましたが。
そうそう、高橋名人の都市伝説もあったようですねw
そんな事で逮捕されたら大変だぁ!
天外魔境シリーズはセガサターン版をプレイして、めちゃくちゃおもしろかったです。
当時はボリュームある大作RPGに憧れていたんですよねぇ。
ハドソンは2000年以降、ゲームファン向けの作品をあまり出さなくなってしまいました。
高橋名人の“都市伝説”。
その「デマ情報」の真相は
1日警察署長の仕事が「警察に捕まった」と誤解されて、それに“尾びれ”や“背びれ”がついてあんなデマ情報に変化してしまった
らしいですね。漫画からの情報ですけど(汗)。そんなデマ情報がインターネットなんてまだ無かったあの時代でも、子供たちの間でのうわさ話レベルで日本全土に広まってしまうんですから高橋名人人気恐るべし!!!
子供たちの伝達力の凄さを思い知らされる話ですねw
読み応えのある面白い記事でした。次回も期待出来ますね
ボンバーマンの顔のデザインのマルチタップとかあったような覚えがあります
ありがとうございます!
次回も超ドラマチックに書いてみせますよー!
マルチタップ懐かしいですね~。ボンバーマンバージョンは今、思い出しましたよw
高橋名人のピークは、
70年代前半生まれだと当時は高校生。
丁度80年生まれだと、ピーク時は小学校上がるが上がらないか。
直撃世代は70年代半ば生まれです。
管理人さんは30前後ですよね?
名人の名残すら無い世代のはずですが。
年齢は伏せますが、
うちはスーパーファミコンをなかなか買ってもらえず、
ずーっとファミコンで育っていたんです。
また、ゲームデビューもかなり早かったので、周りの子と比べたらかなり古いゲームをプレイしていました。
高橋名人はハドソンの広報だったのか!知りませんでした^_^;
「ゲームは1日1時間」は「ゲームだけじゃなく、外でも遊ぼう」という趣旨だったようですが、親にとって都合よく捉えられてしまったようです。kentさんほど厳しくはなかったですが、言われたことはあります。子どもにとっては長年にわたって、嫌な言葉の代表になっていますねw今1日1時間なんて言われても不可能ですw
一番プレイしたのはマリオパーティDSですね。どのミニゲームも面白かった記憶があります。パズルは苦手でしたがw複数人プレイもよくやってました。
ハドソンのゲームは多くやったわけではないですが、なくなってしまうと聞いたときはショックでした。コナミにはもう少し活かしてほしいな〜
高橋名人はハドソンの会社員だったんですねw
セガの湯川専務といい、ゲーム会社の社員がキャラクター化する事はたまにありますね。
少し前だと任天堂の岩田社長もそんなところがありました・・・
あの名言は意図があってのものだったようですが、親には都合よく捉えられてしまって大変でしたよ汗
今のゲームはボリュームがあるので、1日1時間だったらいつまで経ってもクリアできないでしょうね~。
マリオパーティDSをプレイされていましたか!?
このゲームは未プレイですが、シリーズの中では完成度が高いようですね。
僕は幼い頃からハドソンのお世話になっていて、
かなり上位のメーカーというイメージが強かっただけに
1990年代後半以降に凋落していったのは悲しかったです。
こんにちは。
ハドソンと言って思い浮かぶのは、
元祖クソゲーと言われる「バンゲリングベイ」(笑)
やっぱり高橋名人は外せないですし、
あとシュウォッチですね~
昔持ってたシュウォッチは紛失したので、復刻版も買いました(笑)
テレビ番組「高橋名人の面白ランド」「高橋名人のBUGってハニー」も見てましたよ~
高い技術力を見せつけた一方で元祖クソゲーを生み出すハドソンはさすが!w
シュウォッチは連射速度を図るための測定器ですね。
僕は持っていませんでしたが、ハドソンの代表的なグッズなので欲しいです。
昔は高橋名人、メディアミックスも盛んで凄かったですよね。
ハドソンの思い出はあまりありませんが、友達と一緒にボンバーマンをプレイした事はよく覚えています。とても楽しかったですね。スーパーボンバーマンRはあまり評価が良くないみたいなので、次はしっかりとしたボンバーマンを作って欲しいです。
自分は小学生の頃は1日1時間どころか30分だったんですよね・・。今思うととんでもなく短かったです。笑
ボンバーマンは対戦、盛り上がりますもんね!
今でもその楽しさは通用すると思います。
Switch版は見切り発車なのが惜しかった。
1日30分という決まりがあったんですか!?
そうなると大作ゲームは全然プレイ出来ませんね・・・
ゲームソフトも結構「任天堂的」なキャラデザインの奴多いですね。例えば爆弾でお馴染み白い奴とかもそうですし。
スーファミの時に彼にハイジの声優さんの声が当てられ、初代PS時代まで彼女の声でしたが、少しずつ変更されましたね。一番甲高かったのはアニメでも声出した金田朋子さん。アレを原作にした奴も出してましたね。
杉山さんの声一番好きです。漫画的なキャラも色々演じてただけあり面白い声出すのも上手かったですし。PSのボンバーマンの第2段では爆風にやられる時の「うわあ!」という声や顔、そして風船のようにボンバーマンが割れる演出も相まって、動画見た時そこで何度も笑いました。又、OPが凝ってる!キャラにボイス入ってるしフルCGだしショートムービーって感じで。OPと「うわあ!」目当てにゲームアーカイブス入れました(笑)
シャウト
『近所の星から宇宙の果てまで、参上します!ジェッターズ!!』
なぜかお笑い芸人アメリカザリガニのお二人がガング&ボンゴの声を演じていました~!
マックスとしろボンの兄マイティーとゼロの関係がなかなかひねってあって複雑&唸らせたな!!
しろボン
『ボムスターだ!』
そうですね。任天堂と親和性の高いシリーズが多い印象です。
ボンバーマンの声優はよく変わっていますよね。
あまりにも変わりすぎていますが、個人的にはPSやN64の頃が一番好きかなぁ。
今はゲームアーカイブスでPSのボンバーマンを色々プレイ出来るのがうれしいです!
ゲームメーカーを語るシリーズを始めたんですね
自分もやってほしかったと思っていた企画です
ハドソンといったら自分もボンバーマンや桃鉄の
イメージが強かったですね
一番プレイしたのは爆ボンシリーズで一人モードの
難しさにヒーヒー言いながらプレイしてましたw
こうして歴史を振り返ってみるとハドソンって
任天堂への関わりが深かったメーカーだったんですね
コナミに拾われたのは結果的に良くなかったようです
お待たせしました!ようやく始動しましたよ。
今後も大手ゲームメーカーを中心に続けていきたいと思います。
ハドソンと言えばボンバーマンや桃鉄ですね。
それ以前にも人気シリーズはありましたが、2000年頃からはサッパリでしたねぇ。
爆ボンバーマンは高難易度で有名ですよねw
ハドソンはファミコン参入から今日までずっと任天堂と関わりのあるメーカーという印象です。
おお、読み応えある記事ですね。ハドソンは詳しくなかったので、色んな発見がありましたよ。
ハドソンといえば、ボンバーマンとマリオパーティのイメージが強いなあ。どちらも小学生時代に友達とプレイしまくってたので懐かしいです。桃鉄といい、ハドソンはパーティゲームを作るのが上手いですね。
「ゲームは1日1時間」もそうですが、「ゲームしか知らない大人にはならないでください」も高橋名人でしたっけ?
やっぱり当時の子供たちはこの1時間縛りに悩まされてたんですね〜
我が家の場合は、1時間半でしたが週2回ゲーム禁止の日があるといった感じでした。
なので、「うわ、今日ゲーム出来ん日やん、最悪やー」とか登校中憂鬱な気分になってましたよ。
それが今となっては休日とか廃人の如くゲーム出来るようになったと考えるとなんか感慨深い笑
読み応えありましたか!?
今ではハドソンの過去のゲームメーカーですもんね・・・
ここに書いてある事を知らない人も多いと思います。
振り返ってみるとハドソンのゲームはパーティ用としてお世話になりました。
ハドソンのゲームがきっかけで何度喧嘩した事かw
高橋名人は色んな名言を生み出しましたね。
ゲームしか脳のない人間にならないよう抑止してくれました。
今も1時間縛りはあるのかな?
1日1時間半で週2回ゲーム禁止の日があったんですか!?
全く出来ない日があるのは憂鬱ですね・・・そういう日は外で遊ぶしか無いのかな。
確かに昔はゲームのプレイ時間に制限があったと思うと今は気楽で良いですw
ハドソンはただのゲームソフトメーカーではありません。本来ならば、日本のマイクロソフトになるはずだった会社です。
ファミコンに参入する前のハドソンは、黎明期のパソコンの世界において、大手と呼べるほぼ唯一のソフトメーカーでした。もちろんその頃にも光栄やシステムソフトやゲームアーツみたいなところもあったと思いますが、まだ同好会に毛が生えた程度のものだったと思います。なにより大きいのはHu-basicという言語、今で言うところのOSを開発したことだと思います。僕の実家に最初に来たパソコンは、そのHu-basicを載せたシャープ製のものでした。僕にとってのハドソンのイメージはその頃に確立したものです。ハチスケ(ハドソンの蜂のキャラクター)はまだ幼かった僕を、未知のテクノロジーの高い峰へといざなう象徴だったのです。
そのせいか、「おもちゃ」であるファミコンに参入したときには俗な世界に下ったような気がしてものすごく嫌でした。杉山佳寿子さんのかん高い声とともにボンバーマンや桃鉄のCMが流れるたびに、「俺の知ってるハドソンはこんなんじゃない」と、CMに出ている荒井注さんのようにブーたれていたのです。そんな想いを昇華してくれたのが、PC-FXのランチソフトだったTEAM INNOCENTです。FXはポリゴンを否定しているわけではありません。限られた性能の家庭用ハードによるリアルタイム演算にこだわるより、高性能なワークステーションで作った質の高いムービーを使った方がいいという考えなんです。
かつてシャープMZ80-Bのブラウン管の向こうに見たのと同じ宇宙がTIのムービーには見えた。今にして思えば、TIに出会って以降の僕の人生は、ゲーマーとしてはすでに余生だったと思います。あれが頂点だったんです。そこには分析も突っ込みも上げ足取りもコスパ計算もいらない。
必ずしもハドソンと任天堂との関係が良かったとは思えません。ソフトを作る側なら出来るだけよい環境、高いスペックのハードで作りたくなるのは人情。枯れた技術の水平志向を唱える任天堂とはどうしても反りが合わなくなってくる。その結果ファミコンの儲けで理想のチップを設計し、NEC-HEというパートナーと出会う。それはハドソンにとっては課外活動だったかも知れないけど、任天堂にとっては謀叛以外の何物でもなかった。だから裏では任天堂にかなり冷たくされたようで、90年代以降よりを戻して行くなかで全く任天堂に頭が上がらなくなり、そこにメインバンクだった北海道拓殖銀行の破綻が追い討ちをかけて、ハドソンは弱体化していったのだと思います。ルーチンワークである桃鉄とボンバーマン、マリオパーティ以外はろくなソフトがないというか、任天堂ソフトのエピゴーネンをプレイステーションに出す商売しかしていなかった気がします。それでもE.G.G.とかロボットポンコッツ、ルーンジェイドやウェルトオブ・イストリアなど、見所のあるソフトはありました。そして桃太郎まつりは、GTAなどのクライムアクションに対する、日本からの解答だったと思います。
そして最後のハドソンらしいソフトはWiiの影の塔ではないでしょうか。パソコンで出た最初の爆弾男以来続いた「人でなしの物語」の最終章として……。
ええ、ファミコンが発売される以前は
パソコンゲーム市場で圧倒的なソフトシェアを占めていましたから、その可能性はあったと思います。
高スペック路線だったのも確かで、一時期までは最先端を走っていたメーカーという印象です。
会社の方針は任天堂と食い違っていたところはあるので、
タイミングが悪かったら犬猿の仲になったかもしれませんね。
影の塔はハドソンのゲームなんですよね。
この頃まではデカスポルタのヒットでWiiに挑戦的なゲームを色々出していましたよねぇ。
買わなきゃハドソン!
バンゲリングベイでハドソ〜ンと叫ばされた世代ですよ
スターフォースやスターソルジャーが流行ってましたなぁ
ハドソンは、pcエンジンから看板となった対戦ボンバーマンと桃鉄しか作らないイメージになっちゃいましたね。
pcFXは友人が持ってましたが、エロゲのイメージしか無いですな(笑
さすがつぐみ先生!w
高橋名人といえばスターソルジャーのイメージも強いですね。
ハドソンのゲームは色々プレイしたけど、
いつの間にか桃鉄とボンバーマンしか残らなくなってショックでした。
ハドソンはPC事業でシャープと蜜月の関係にあり、任天堂もゲームウォッチ時代にシャープと付き合いがあった関係で、任天堂とハドソンもつながりが強かったようですね。
任天堂もハドソンに関してはかなり、優遇措置をとっており、ファミコンの黎明期には多大な貢献をしています。
たしか、本体かカートリッジの設計の一部にも口出ししていたと思います。
そして、ファミコンの性能限界を感じ、NECと共同でPCEを作るに至ったわけですが、これができたのは正直バブル経済の恩恵で金余りだったことによるところも大きいでしょう。
実際バブルが崩壊した後は、NECがPCEの市場を支えきれず最終的に撤退することになります。
あと80年代あたりは知的財産権がかなりあいまいな時代でもあり、いろいろドロドロした話も出てきて、その辺でもちょくちょく名前が出て聞くることがあります。
ハドソンは、技術屋集団で移植技術などはすさまじいものがあったのですが、悪く言えばオリジナルティに欠けるところがありました。
ボンバーマンと桃太郎シリーズ、天外魔境シリーズを除くと、元ネタがあるか移植であることが多く、独自性に欠けるものが多かったのも事実です。
例えば、ナッツアンドミルクはドンキーコングのパクリ、ロードランナー、バンゲリングベイはブローダーバンドからの移植、スターソルジャーはスターフォースが元になっていて、そのスターフォースもハドソンは移植しただけで作ったのはテーカン(のちのテクモ)でした。
この辺が、桃電、ボンバーマン頼みになってしまったところだと思います。
たらればの話ですが、山本大介氏がハドソンを退社せず、もしハドソンがパズドラを出せていれば事情が変わったかもしれませんが・・・。
そうでしたそうでした!任天堂はハドソンにかなりの優遇をしていましたよね。
さすが、ファミコン初期の頃から関わっているだけの事はあります。
その縁もあって今日まで良好な関係が続いているんでしょうね。
バブル時代の話は今、思うと信じられません。
そこまでみなさん、お金が余っていたとは。
確かにハドソンはオリジナリティに欠ける印象です。
2000年以降も色んなジャンルの要素を融合した欲張ったタイトルばかり出していた印象で、革新性には欠けましたから。
私はハドソンというメーカーを小学4年(2004-2005年頃)あたりに知った人なので、80年代当時のハドソンがとても技術力が高かったことに驚きました。確かにハドソンは私もボンバーマン、桃鉄の二つぐらいしかイメージがわかないのでPC-Eやスーファミ時代にとても輝いていたメーカーだったかと思いました。ロードランナーがファミコン初のサードパーティであることは知っていましたが、こうやって記事で振り返ると任天堂との関係は厚いですね。PC-Eの頃にソフトを供給してたので一時期スクウェアのように仲違いしてたのかなと思ってましたが、スーファミやGBにも同時期にソフトを提供していたのですね!企業としてみれば、とてもいい企業なんだけど、ボンバーマンや桃鉄は理不尽な難易度とハンデなどの救済処置がないので私の周りではクソゲーと言われてましたね(^^;;(ケントさんの世代では信じられないかもしれませんが…)近年の桃鉄でも言えますが、このように新規のユーザーの声をあまり取り入れないでほぼ昔ながらの体制でソフトを作ってしまっていたという点がこの企業の欠点かもしれません。ボンバーマンはスイッチでは残念な結果でしたが、任天堂がライセンスを得たという点でももしスイッチで桃鉄を出すのだとしたら、貧乏神なしもしくはキングボンビーの変身なし、歴史ヒーローオンオフなど現代のユーザーのニーズに合わせて任天堂が堂々と発売できる”面白い”桃鉄に仕上げてほしいと思います!
トモフミさんの世代くらいになるとハドソンは大手ゲームメーカーのイメージもないんでしょうね・・・
僕は一時期までハドソンは任天堂と並ぶメーカーだと信じていたので、
PSやN64が出てきた頃から目立たなくなってきたので驚きましたよ。
PCエンジンはよくファミコンのライバルとして挙がりますが、
今のPS4とSwitchみたいな関係とはちょっと違うんですよね。
ボンバーマンや桃鉄は理不尽に感じていましたか!?
ふーむ・・・新規のユーザーならではのご意見ですね。
確かに分かっている人だけが買っている感じがします。
PSで完全新作のヒットを飛ばせたかどうかがハドソンと、コナミやナムコやカプコンの分かれ目になったのですね。ハード事業に関わってたことも結果的にマイナスになっちゃったのですかね。
コナミの傘下に入るより、もし入れるなら任天堂の傘下に入ったほうがハドソンにとっては幸せだったような気がします。
そうですね、ハドソンはPSで完全新作のヒットを出せませんでした。
KONAMIやナムコ、カプコンは生み出せていただけに、そこで明暗を分けたのは確かです。
ハドソンは任天堂の子会社になったほうが良いと思うなぁ。
ゲームメーカーに焦点を当てた記事、面白いですね!高橋名人に会ったことがあるなんて羨ましいですw
自分は北の方出身なので、ハドソンは昔から馴染のあるメーカーで思い入れも少なからずあります。でもSFC~64世代のせいかハドソンと言えばもっぱら桃太郎シリーズとボンバーマンのイメージですね。SFCの新桃太郎伝説は今でも好きな名作です。PSSS64時代は第一線から後退はしましたが、爆ボンバーマン等楽しんでました。でも良い作品も微妙な作品もやたら乱発してた時期の気がします。PCエンジンはまったく遊んだ事が無かったのでWiiのVCで初めて触れてけっこう感動しました。
近年の復活は嬉しいです。こういう広く知れ渡ってる有名IPはしっかり活用していって欲しいですね。
うろ覚えですが、子供の頃デパートの屋上でやってたハドソンゲームイベントに行ったことがあります。あの頃は元気だったんだろうなあ・・・
今後もメーカー特集楽しみにしてます!
ありがとうございます!
初めての試みでしたが、コメント欄を読んだ感じでは大好評なので良かったです。
そう言えばナッツさんはハンドルネームとは裏腹に北の方に住まれていましたね。
ハドソンとの親近感もわかります。
僕も爆ボンバーマンは楽しんでいたなぁ。でも、ボンバーマンヒーローは微妙でした。
PCエンジンソフトは僕もバーチャルコンソールで触りましたね。
ハドソンのゲームイベントですか?
昔は独自で色々開いていましたよね~。
次回もナッツさんの琴線に触れる記事になりそうですw
例の番組があった後だからか、凄くタイムリーな話題w
ハドソンのコンテンツは桃太郎、ボンバーマン、天外魔境、
筆頭に色々とお世話になりましたね。PCEとか凄まじい
存在感だったのは今でも脳裏によぎりますね。
ロードランナーはあまり馴染みは無いけどあのスペランカー
と同じブロードバンド社系列のゲームと知って驚いたな。
高橋名人の冒険島も実は原作があって、先日配信された
ワンダーボーイシリーズの一つが元となっているんですよ。
原作よりアレンジ版のが有名になるというのも色んな意味で凄い。
昔のハドソンを知る人にとっては、2000年過ぎてからの
開発力の低下、最終的に消滅という流れは現実として
なかなか受け止められなかったですね。
旧ハドソンのコンテンツはどうなってしまうのだろうか
と思いつつこうして立て続けに復活してくれただけでも
今は十分かな。可能であれば旧作のVCやら何とか配信に
向けて動いて欲しいけど。
例の番組、見ましたが、かなりハドソンの事に触れていましたもんね。
確かにこれはタイムリーな記事になれたと思います。
Ryouさんはハドソンの3大看板タイトルにしっかりと触れていたようで、思い入れがありそうですね。
そうそう、ワンダーボーイが原作なんですよね。
ますます、ワンダーボーイが気になってきましたよ。
シリーズが枝分かれしていくところは興味深いですね。
ハドソンのコンテンツは今後も細く長く行きてくれそうです。
やだ…おっさんホイホイ過ぎる…。
他の方々が挙げているタイトル以外で思い出深いのはFCの迷宮組曲です。
ゲーム自体も程良い難易度のアクションゲームですが(コンティニューコマンド失敗は語り草)、何と言ってもボーナスステージ。楽器箱を取ると入れるステージなんですが、取って行くに従ってどんどんBGMで使われる楽器の数が増えてゆく。最初はスネアドラムだけだったのがベース音のチューバが入り対旋律が来て最終的に主旋律が入って「これこんな曲だったのか!」と子供ながらに感動しました。正直このボーナスステージのみでタイトル回収してる気がしないでもないです。
しかもこれFCだから3音+ノイズ1音しか同時に出せない訳です。なのに見事に音数管理してちゃんと楽器の数が多い音が分厚い曲に仕立て上げてるんですよ。これを大人になってから知り、更に凄さを思い知りました。
PCEだと、移植ですけどイース1・2ですかね。他機種が色々頑張ってスペックダウンさせて移植してるのに、これだけボイス入り音楽豪華のオーパーツ振りw おかしいだろやりたいに決まってるだろ…。
逆にディスクシステムだとぱっと思い浮かぶゲームがないんですが、あまり出してなかったんですかね?FCDだとコナミが印象深いなあといずれ出てくる話題でしょうか。
とまあ色々思い出深いんですが、後にメーカーとしてのハドソンが消滅してしまった時には諸行無常だなひとつの歴史が終わったなと思いました。
何だかんだでコナミにがっつり拾われてるだけ(アイレムとかより)まだマシなんでしょうが、その親会社さんには色々塩漬けせずにVCなどの展開をお願いしたいものです。まあVC化出来ないのは、版権とか著作権の問題とかもあるのかもしれないので、コナミばかり責めてもいかんのかもしれないですが…。
ファミコン用ソフト「迷宮組曲」!
『何と言ってもボーナスステージ。楽器箱を取ると入れるステージなんですが、取って行くに従ってどんどんBGMで使われる楽器の数が増えてゆく。(中略)最終的に主旋律が入って「これこんな曲だったのか!」と子供ながらに感動しました。』
先日見た“ユチブ”のプレイ動画にもその解説文付きでボーナスステージが収録されていました!!“オカリナ”のパートが加わった時の“劇的な”変化に注目!だそうですよ!確かにあれはちょっとした「!」ですね!!
返信失礼しました。
ハドソンに馴染みがある人はもう、おっさんばかりになるんでしょうねw
迷宮組曲は知りませんでしたが、情報を見た感じだと面白そうです。
昔はハドソン、こんなゲームを出していたのか。
当時、楽器を全面に押し出したアクションゲームって珍しいと思います。
イースの移植話は当時の技術力を感じますね。
ディスクシステムのハドソンゲームは言われてみると思い浮かばない。
PCエンジンと時期が被るから出せなかったのかな?
ハドソンブランドが終焉した時は悲しかったですねぇ。
ブログでも色々書いた記憶があります。
昔(SFC〜64時代)は任天堂の次にお世話になっていたゲームメーカーでした、PCE,SFC,64,PS,SSで発売されたボンバーマンや桃鉄をやり込みまくっていました、なのでハドソンの吸収合併を聞いた時はとてもショックを受けました。
その後桃鉄やボンバーマンの新作が出ませんでしたが最近になって新作が出ると聞いた時はとても嬉しかったです、出来は両方共期待外れでしたけど桃鉄はV以来16年ぶりでこれも変化だと受け止めれば許容できますし、ボンバーマンは最初はお察しの通りでしたけどアップデートでだいぶ良くなってきたのでなんだかんだ言ってエキスパートも★3つコンプを目指すつもりになりました。
こうして見ると任天堂とハドソンの縁がかなり深いなと感じますね、マリパをプレイしてたらハドソンのロゴが出てきたのもそれでしたし。
ボンバーマンは全ハードまんべんなく発売されていましたもんね。
かつてのハドソンはヒットタイトルをあらゆるハードで出していたなぁ。
最新作は残念でしたが、復活しただけでも嬉しいという気持ちはあります。
振り返ってみて任天堂との繋がりを強く感じたので記事タイトルにも付けてきました。
小学生の頃は良くボンバーマンで遊んでいておそらく対戦ゲームの中では一番プレイしていたシリーズだと思います。
個人的に復活したと思うゲームメーカーはSNKですね。
去年発売されたKOF14を皮切りに新作を作るそうなので今後が楽しみなメーカーです。
ボンバーマンは当時のパーティゲームでは代表格でしたもんね!
ストリートファイターIIよりもとっつきが良いですし。
SNKもいずれは特集したいです。
興味深いシリーズですね。スパイクもPCエンジン時代からいい仕事してました。
今後もゲームメーカー特集をやっていきます。スパイクもいずれやりたいですねー
ハドソンのゲームはどの時期のも面白いんですけどねー
ボンバーマンシリーズや桃太郎シリーズ、天外魔境シリーズだけじゃなく、
デカスポルタシリーズ(記事にもありましたが)とかコロリンパとか、絶対音感オトダマスターや影の塔といった末期作品も十分面白い。
宣伝と流通が弱かったかな、というところですかね。
一時期ほどは宣伝も弱くなっていましたもんね。色々、悪循環が巻き起こっていたと思います。
『ちなみに高橋名人とは実際に会った事があります。子供の頃から憧れだった高橋名人に会えた時は嬉しかったなぁ。』
?!うわ~うらやましい!!しかもツーショット写真まで!!!(こりゃ疑う余地なしだな!)とても「ちなみに」レベルの話じゃないですよ!!ケントワールドさんにとっての小さな、いや、大きな自慢じゃないですか!!
わ、私だって高橋名人と
“キャラバン会場内で一緒に同じ時を過ごした”
んだぞぉ~!・・・ってそんなのはな~んの自慢にもなら~ん!!ぶっちゃけ予選には誰でも参加できたんで!!もち敗退!!
あらし
『炎のコマ~!!!』
おお!ご覧になりましたか!?たまたまではありますが、とても嬉しい出来事でした。高橋名人はネームバリューがありますよねー!
わ、私だってあの阪田雅彦さんに会ったことがあるんだからね!なんせ私は・・・おっとこれ以上はまだヒミツ♪
ファミリーベーシックってファミリーコンピュータ(以降ファミコン)が発売される前から開発が始まっていたのか!さらにその開発にハドソンが参加していたとは!!その開発知識のノウハウと技術の蓄積があったからこそハドソンはファミコンのサードパーティーにライバルメーカーをさし置いていち速く参入できたのだ!!!
・・・というゲーム史の真実を先日“ユチブ”動画で知りました!!
私はコロコロコミック別冊の漫画(書籍?)を読んでハドソンの歴史を学んだつもりでしたが、このファミコン参入の過程についてはまだ知らなかったので驚きました!
ならば自社で開発したPCエンジンならなおさら専用ゲームソフト開発がしやすかったんだろうな!!ハドソン恐るべし!!これも“運命”だったんだろうな。コナミによって吸収消滅する最後も含めて・・・あんな偉大なゲームソフト開発メーカーをなぜ救わなかった任天堂?
と思ったんですが、あなたの記事を読むと(今でも)ハドソンと任天堂の絆は強いらしく親密な関係は今も続いているみたいですね?また何かしらの“助け舟”を・・・2020東京オリンピックゲームの開発チームにでも呼んであげたら?!
と、まずはハドソンがファミコンのサードパーティに参入する部分だけに反応してみました。
ハドソンに関しては今となっては信じられない話がいっぱいあります。
ハドソンがトップを走っていたのは1990年代前半まででしょうね。
それ以降はトップから退いてしまった印象で、2000年代に入る頃にはBクラスのゲームメーカーに感じました。
助け船を出せなかったのはその辺りに理由が隠されていそうです。
先日。
アーケード版「スターラスター」について調べようと思ったら“ユチブ”で「ソルバルウ」プレイ動画に“寄り道”してしまった私はその後・・・ファミコン用ソフト「迷宮組曲」のプレイ動画に釘付けになってしまった~!!
その発見につぐ発見!&ステージの変化につぐ変化!に没入してしまい見ることを途中でやめられない!!完全に脱線だぁ~!!
このゲーム!あの「スーパーマリオブラザーズ」に匹敵するほどの『発見』が隠されています!ゲームに(過度な?!)“リアクション”を求めるケントワールドさんも満足できる内容の詰まった「謎解きゲーム」ではないかと思いますよ?
「迷宮組曲」についてコメントした人の返信にも書いたように、ボーナスステージの“♪変化♪”に、知っていたはずの私も思わず「!」してしまった!!オカリナ~♪
このゲーム!私も昔、よく遊んだなぁ~!!そんでもってある日、本腰を入れて攻略本を片手にプレイして多分一応クリアできたんじゃなかったかな、と!なぜなら今回のプレイ動画の画面を見ていて懐かしい気分に浸れたってことは、少なくとも過去に一度は「見たことがある光景」だったということになりますから!クライマックスのボスとの対決シーンもうろ覚えながらも見覚えがある気がしましたからね!
それにしても長い。これじゃ電源を切らずにプレイしても『ゲームは1日1時間!』でクリアは無理ですよ高橋名人?・・・そしてエンディングは唐突に訪れた。
長かった~!!でも充実した内容だった!!
・・・あはは、アーケード版「スターラスター」のことはすっかりそっちのけだ~!(汗)
というわけでハドソンの「迷宮組曲」でした!
あと、この「迷宮組曲」ってファミコン以外にも移植されているみたい?!そんな映像を見ました。「ミロン」のゲーム内容までは未確認です・・・。
昔のゲームは裏技を多く入れることがステータスになっていた気がします。
発見は楽しいですよねぇ。隠しキャラが出てきたら「あっ!」て思います。
私が自力で隠れキャラを発見して思わず「あっ!」て思ったのは
ファミコン版
「レッキングクルー」
のスペシャルハンマー!!!
でして・・・とここはハドソンの記事のコメントでしたね。では今回はこのへんで・・・
ファミコン用「ファザナドゥ」、“「ザナドゥ」への道”?!
★★★★★★★★★★★★★★
“ファミコン版「ザナドゥ」”とは呼ばれていない(!)「ファザナドゥ」をPCエンジン版「ドルアーガの塔」と同等に進化&リメイク移植したらきっと“PCエンジン版「ザナドゥ」”と呼ばれるような作品になるんじゃないかな!
とりあえずはプレイヤーキャラのステータス&パラメーター設定を再構築し直して、RPGならば当たり前な
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
経験値を貯めたらレベルアップしてパラメーターの数値が上がって強くなる
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
仕様にしないとな!!
最初から体力&魔法のゲージ表示の長さがMAXのまま変わらないというのは寂しい!レベルが上がるに従って少しずつ長くなる仕様にしないと!もしくはパラメーターの数値を上げていき、ゲージはその数値全体の何パーセントの割合なのかを表示する仕様にするか!
体力と魔力のステータスにダメージのステータスを追加!
ダメージは文字通りに敵との戦いで受けたダメージ(数値&ゲージ)を表示。体力は時間がたつ毎に徐々に減っていき、なおかつ激しい戦闘をすると更に減る仕様に変更!
ダメージは医者に治療してもらい、体力は“このゲーム名物”の乾燥肉を食べて回復!これなら病院と肉屋が共存できる!
魔力は「道場」で回復!魔法もただ購入するのではなく、この「道場」で与えられた試練をクリアすることで会得できる!
おっ?!いい感じになってきたじゃないか?何?!ゲームをプレイする側としては面倒くさい仕様だって?まあ、そう思われても仕方ないか。
でも乾燥肉&体力ステータスの役割ってこのゲームの開発当初はそんな設定になる予定だったらしいゾ?!
さらに登場キャラクターたちのデザインもエルフ族やドワーフ族の特徴がわかる姿に設定し直して!
ドワーフ族が変異した姿になった敵キャラクターも種類を増やして!
もう少し舞台&ストーリーのスケールを大きく拡げて!
せっかく世界樹(せかいじゅ)というファミコン版オリジナルの世界観設定が評判いいんだからさ!これを活かさない手はない!!
ファミコン版の特長としてこれまた評判のBGMとあの「大きな文字表示」のメッセージ画面は引き継いで欲しいかな!
・・・よし!!
PCエンジン版「ファザナドゥ」
の移植計画発動!!
★★★★★★★★★★★★★★
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
この強化移植ならきっと“ファミコン版「ザナドゥ」”の移植版として“PCエンジン版「ザナドゥ」”の称号を手にすることができる!!はれて(移植されて生まれ変わった)「ファザナドゥ」が「ザナドゥ」と認められてシリーズの仲間入りができるんだ!!ファミコンディスク版「リンクの冒険」に勝るとも劣らないアクションRPG作品にもなれるぞ?!
あ、“おっさん要素”は残しても構わないよ!(笑)
・・・てな妄想をしてみました~!だがこのわしに改造&移植できる実力などない!!!仮に移植できたとして、PCエンジン版なのに「ファザナドゥ」とはこれいかに?!でもゲーム名を変えたら強化移植の意味がなくなるぅ~!!
最後に言い忘れたが、わしはパソコン版「ザナドゥ」のことは少し知っているだけでプレイしたことはないぞ!!(自爆!)