
どうも!KENT(@kentworld2 )です!
ふと、ゲームソフトの情報をWikipediaで調べてみると以下のようなジャンル名が表記されていました。

PS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV 」の場合はアクションRPG。

Switch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 」の場合はアクションアドベンチャー。
前半の単語は共通していますが、後半の単語は異なっています。
アクションRPGとアクションアドベンチャー。
一体、どう違うのでしょうか?
本記事ではアクションRPGとアクションアドベンチャーの違いについて語っていきます。
目次
プレイヤーを育てるゲームなのか?ゲーム内キャラクターを育てるゲームなのか?

アクションRPGとアクションアドベンチャーの違い。
ズバリ、プレイヤースキルかキャラクタースキルのどちらを重視しているのかで決まるのでしょう!(丸尾くん風)
簡単に言えばアクションRPGはプレイヤースキル<キャラクタースキル。
アクションアドベンチャーはプレイヤースキル>キャラクタースキルだと思っています。
PS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」とSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」。
どちらのゲームにも成長要素が存在します。
こうして見るとどちらもRPGのように見えますが、バランス調整が全然違うんですよ。

PS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」の場合、敵を倒すと経験値が溜まり、レベルが上がります。
それを繰り返していくと様々なパラメーターが上がり、それまで戦っていた敵を簡単に倒せるようになるんですよ。
攻撃を受けても1ダメージしか受けないでしょうし、反撃したら1,000ダメージを与えて一発で倒せてしまうでしょう。
その際、プレイヤーが行ったのは攻撃ボタンを押すだけです。
強くなったのはゲーム内キャラクターであって、プレイヤーではありません。
さらに装備の概念によってパラメーターの数値を何倍にもすることが可能なので、いくらでも強化出来ます。

一方、Switch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の場合、敵を倒しても経験値が溜まってレベルが上がることはありません。
ただ、祠を攻略することで体力やがんばりゲージの最大値を増やせますし、装備の概念によってパラメーターの数値を何倍にも出来ます。
最弱と最強の状態では何百倍もの差が生まれるでしょう。
しかし、そこまで行くには相当な数の探索をこなさなければならず、プレイヤースキルが求められます。
PS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」とSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」。
どちらも3Dのオープンワールドアクションという点は共通していますが、バランス調整は全く違います。
PS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」の場合はプレイヤースキル<キャラクタースキル。
Switch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の場合はプレイヤースキル>キャラクタースキルと言えるようなバランス調整となっています。
決め手となるのは攻撃力

プレイヤースキル重視なのか?キャラクタースキル重視なのか?
その決め手となるのは攻撃力だと思っています。
僕の中でのRPGって時間さえかければアクションに自信が無い人でもクリアできるバランスのゲームだと思っているんですよ。
そういったバランスのゲームって大抵は攻撃力の成長要素が強いケースが多く感じます。
レベルを上げたり武器を強化することで何十、何百倍も攻撃力が上がっていく。
ということは、逆に言えば強化をしなければ大量の攻撃を敵に当てなければならず、戦闘が終了するまでに物凄い時間がかかってしまいます。
そうなると相当な根気が必要ですし、ゲームによってはタイムオーバーで倒せないかもしれない。
そんなバランスのゲームは例えキャラクターを直接操作して攻撃が出来たとしてもぼくはアクションRPGに感じてしまいます。

逆に攻撃力の成長要素が低いゲームはどうでしょうか?
いくら防御力や体力が低かったとしてもプレイヤーの腕さえあれば回避でなんとかなりますから、成長要素があったとしても強化せずにクリアできるでしょう。
現にSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の場合、実質的な成長要素は体力とがんばりゲージしかありません。
あとは探索することで見つかる装備品で何とかなってしまいます。
その最たる例が正当法で1時間未満クリアができることです。
こんなこと、プレイヤースキル>キャラクタースキルのバランス調整じゃないと出来ません。
↑当ブログはゲームレビューしたタイトルをジャンル別に分けています。
その中にはアクションRPGとアクションアドベンチャーもありますが、本記事のような形で区分しています。

ですので、PS4「仁王」はアクションRPGのカテゴリーに。

PS4/Xbox One「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」はアクションアドベンチャーのカテゴリーに入れました。
これらのゲームは高難易度アクションRPGとして知られる「DARK SOULS(ダークソウル) 」から派生したSOULS-Like(ソウルライク)ゲームになりますが、バランス調整が全く異なっていたんです。
頭を使うのがRPG。指を使うのがアクションという見方もできる

ここまでアクションRPGはプレイヤースキル<キャラクタースキルであると書きました。
しかし、考え方によってはプレイヤースキル>キャラクタースキルにも感じます。
ぼくが考えるプレイヤースキルとは、あくまでも”指”を駆使した操作に関するものなんですよ。
でも、着眼点を”頭”に持っていくと前提が大きく変わっていきます。
確かにアクションRPGは経験値を稼いでレベルを上げていかないと火力不足に陥って苦戦してしまうかもしれません。
が、属性の概念を理解すれば低レベルでもクリア出来てしまうことも多いんですよ。
例えば炎属性の敵に水属性の魔法攻撃を当てると2倍ダメージを与えられるとか。
属性の概念を理解するには”頭”を使わなければなりません。
ですので、低レベルクリアを意識する場合、“頭”を使うのがアクションRPG。”指”を使うのがアクションアドベンチャーという見方も出来ます。
収斂進化によって見た目が似てきたFFとゼルダ


PS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」とSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」。
そもそも、両者はどうしてこうも似て非なるバランス調整になっているのでしょうか?
「3Dアクション」「オープンワールド」「成長要素」と共通点は沢山あるのに・・・。
それは、収斂進化(しゅうれんしんか)によるものだと思っています。

「ファイナルファンタジー」の1作目は「ドラゴンクエストI」の影響を受けて作られました。
「ドラゴンクエストI」は「コマンド式のバトル」「成長要素」「グラフィックアドベンチャー」を融合させたようなゲームになります。
「ファイナルファンタジー」シリーズは作品を重ねる毎に独自の解釈でこれらの要素を融合していきました。
戦闘は徐々にリアルタイム要素を重視していき、グラフィックは3Dになり・・・。

その結果、ナンバリング15作目となるPS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」はリアルタイムのアクションバトルになってエンカウントも廃止されました。
さらにマップはオープンワールド式を採用。高い自由度を実現しようとします。

一方、「ゼルダの伝説1」は「アクションバトル」「グラフィックアドベンチャー」を融合させたゲームになります。
それも1作目の時点で戦闘パートと移動パートのシームレス化を実現していたんです(リンクの冒険は除く)。

ただ、作品を重ねる毎にグラフィックが2Dから3Dに進化してSwitch/Wii U「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」に至ってはマップがオープンワールドになります。
その結果、同時期に発売されたPS4/Xbox One「ファイナルファンタジーXV」と表面的な部分が似てきてしまったんです!
全く系統の違う動物が似たような体形をもつことを収斂進化と言いますが、「ファイナルファンタジー」と「ゼルダの伝説」はその典型例と言えるでしょう。
全体のまとめ

以上!アクションRPGとアクションアドベンチャーの違いを語ってみました!
ゲームも進化が進み、各ジャンルが同じ方向へ進もうとしています。
リアルタイム性を追求し、シームレスや自由度も追求していく。
その結果、アクションRPGとアクションアドベンチャーの区別が難しくなってきました。
今回、識別法を紹介しましたが、あくまでも個人的な解釈に過ぎません。
ゲームジャンルの認識はゲームメーカーによってまちまちですし、販売戦略のためにあえて異なるジャンル名を使用することもあるでしょう。
例えば実際にはアドベンチャーゲームなのにRPGと表記するとか。
日本人の場合、RPG好きが多いのでジャンル名にRPGを付けると注目を集めやすく感じます。
かくいうぼくも一時期は「ゼルダの伝説」シリーズを友達に紹介する際はアクションRPGと言い張っていましたw
N64「ゼルダの伝説 時のオカリナ」発売時に公式が稀にアクションRPGと謳っていたことを受けて言い張っていたんですが、やっぱりRPGと付くだけで友達は反応するんですよ。
こういう「物は言いよう」精神がゲームジャンルの区分をややこしくしているような気がしますw
▼最後に3行まとめ
- アクションRPGはプレイヤースキル<キャラクタースキルのバランス調整。
- アクションアドベンチャーはプレイヤースキル>キャラクタースキルのバランス調整。
- 低レベルクリアを意識した場合、”頭”を使うのがアクションRPG。”指”を使うのがアクションアドベンチャーという見方もできる。


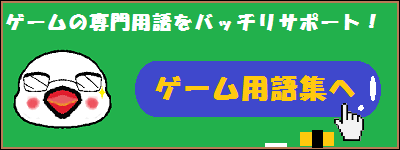
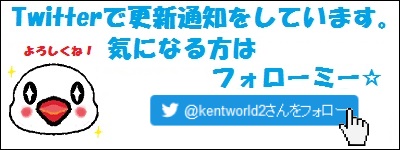
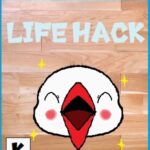


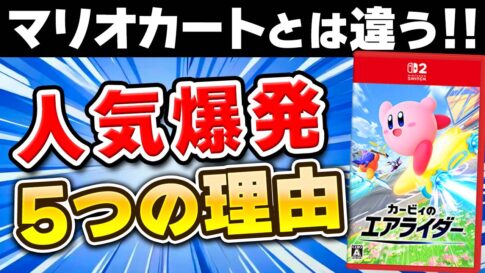

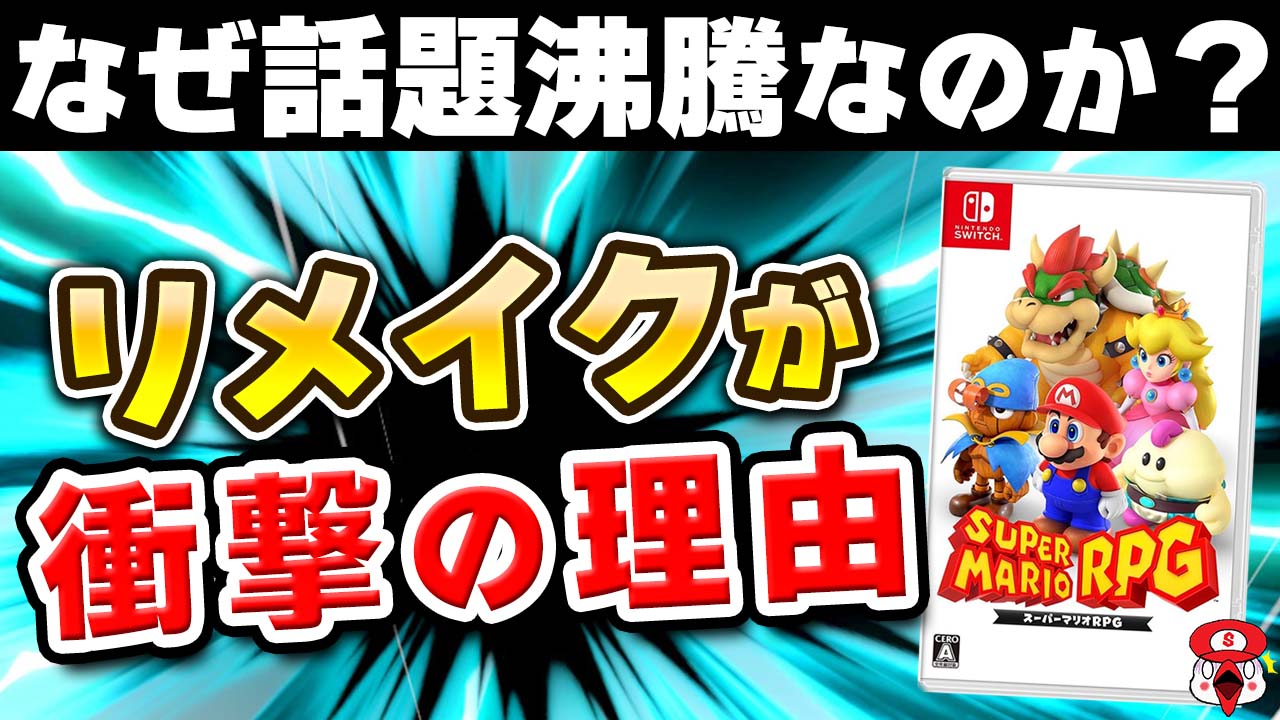
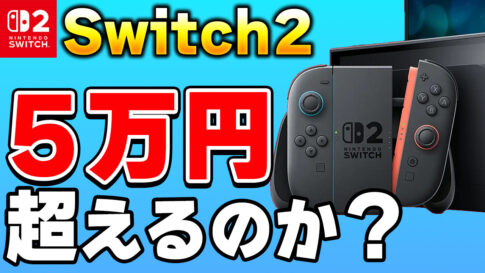




今の時代はグラフィックの進化によって、もともと異なっていたジャンルが同じようなものに見えてしまいかねなくて、そこで「〇〇ではできるのになんでこっちはできないんだ!(実は〇〇は別ジャンルの派生)」問題が生まれてしまいましたよね。
実際、僕もゼルブレは「アタリマエ」の見直しで前作からゲーム性が変わったために「どうせなら、経験値要素をつけて自キャラが強くできればいいのに」と思ったことがあるのですが、これは「ゼルダ」のアイデンティティの上では変えてはいけないラインだったのでしょうね。
今回の記事を読んで僕はアクションADVよりアクションRPGの方が好きなジャンルだなと思いました(^^)
妖怪4は前作からガラッと変わりましたが、このジャンル変更が個人的に好感触だったかも♡
そうなんですよ、ぼくも同じようなことを思ったことが何度もありますから。
出来ないことを出来るようにするのがゲームですからそれは間違っているとは思いませんが、シリーズがどのように進化をしたのか調べると納得出来ることもありますよね。
今後のゼルダに経験値要素が搭載されないとは限りませんが、搭載されたとしても大した成長要素にはならないんじゃないかと思っています。
妖怪ウォッチ4はアクションRPGでしたね。個人的にもオートバトルよりも好感触です。
なるほど、ブレスオブザワイルドの二週目がやたら面白く感じたのはこういうカラクリが…!
kentさんのこういう記事好きです(꒪꒫꒪ノノ”
ありがとうございます!このお題、ずっと言語化したかったんですよー。
昔はアドベンチャー言うたら、テキスト系のノベルゲーか多かったんですけどね
最近はジャンルが多様化しすぎていて区別しづらいったら(笑)
RPGとの区別は経験値入るか否かって感じかな
本来のロールプレイの意味がよくわからんくなってますしな。
自分は経験値でどうにかなっちゃうステータスゴリ押しゲームは最近苦手な感じなんで、アクションアドベンチャーの方が好きかなっていうか、アクションゲームとアクションアドベンチャーの違いはなんやろか?
アドベンチャーゲームも多様化していて分かりにくくなっていますもんねw
>アクションゲームとアクションアドベンチャーの違い
ここで言うアドベンチャーゲームはコマンド選択式の探索型アドベンチャーを発展させたものだと思っています。
そういった要素がない。もしくは薄いスーパーマリオの場合はアクションゲームになるんじゃないかと。逆にゼルダの伝説は本質にも関わってくるのでアクションアドベンチャーになります。
本来、アクションとアドベンチャー、RPGは相反するものですからね
一方でRPGとアドベンチャーの境界は曖昧です
(そもそもアドベンチャーゲームの定義自体が曖昧)
ゼルダは最初からアクションアドベンチャーと名乗っていましたし、RPGを自称したことはなかったと記憶しています
最近だと経験値の要素があるものはアクション要素の有無に関わらずRPG、という考え方が一般的なので経験値のないゼルダはアクションRPGではない、という方が分かりやすいかな
そもそもアクションとアクションアドベンチャーって何が違うんでしょうねw
ホロウナイトみたいな探索型のアクションゲームは(メトロイドヴァニアという呼び方はおいといて)アクションアドベンチャーにカテゴライズされるのでしょうか?
実はぼく、アクションRPGという言葉を覚えたのが時のオカリナなんですよw 公式なのか忘れましたが、当時のゲーム雑誌かなにかでそういう表記を見たことがあります。
>そもそもアクションとアクションアドベンチャーって何が違うんでしょうねw
つぐみさんのコメントでも返信しましたが、コマンド選択式の探索型アドベンチャーを発展させた要素の有無だと思っています。
なので、探索型アクションゲームの中でも洞窟物語などは該当すると思いますが、それ以上にメトロイドヴァニアの色が強いので探索型アクションと名乗っているんじゃないかなと。
アドベンチャーってよくよく考えたらかなり定義があいまいな気がしますね。
ADVっていったらテキストを読んでいって進めていくイメージなんですけど、アドベンチャーって言った瞬間そうとは限らないんですよね。
RPGも基本的なJRPGてきな物から、海外風のRPG的な物まで様々ですからね。
逆にそこまで区別しなくてもいいのかも・・・アクションはもちろん区別しないとダメですけどwww
アドベンチャーゲームも枝分かれしましたからねぇ。
最近はテキスト主体なのがメインなのは確かですが、古くはコマンド選択式の探索型が主流なんですよ。
ジャンル表記で使用されるアドベンチャーはそちらを意識しているものだと思われます。
RPGはさらに細分化が進んでいますが、こちらはJRPG、SRPG、育成RPGなどいくつかの表記が作られています。
一応、アドベンチャーゲームもテキスト主体のはADV。探索主体のはAVGと分けられているものだと思っているんですが、ほとんど浸透していません。
AVGとADVで違いがあるなんて寡聞にして知りませんでした!
単に切り方違うだけかと…
是非切り方と意味の因果関係とか教えてください
因果関係ですか?
AVGは古いメディアで使われていてADVは比較的最近生まれた略称だからです。
最近のアドベンチャーゲームはビジュアルノベル系が多く、昔はコマンド選択式のグラフィックアドベンチャー中心だったので、そこが因果関係になります。
単純に考えると
RPGは主人公主観で進む成長要素のある物語
アドベンチャーは舞台主観で進む成長要素のない物語
と言うことではないかと。
某ゲームは育成アドベンチャー(通称育ベンチャー)と名乗っていた事を考えると、本来アドベンチャーにはRPGの様な育成要素がない物であるとも考えられる。
ややこしいのは育成やら恋愛やらついたのが多いSLGの方だろうな。
元々シミュレーションにはパラメーターが存在しているにも関わらず、戦略SLGやら代名詞が先についていることで二重修飾なのやも知れん。
ユーザーが一目で何のSLGであるか指向性(嗜好性?)をわかりやすいと言う点に置いては有効なのだがね。
ぼくもそういう認識だったんですが、最近はアクションアドベンチャーでも成長要素を加えた作品が増えてきたのでややこしくなってきました。
シミュレーションもややこしいんですが、こちらはタイトルの総数自体が減っているという問題ががが。
僕は成長要素がレベル制などのパラメーターを重きに置いた作りがアクションRPG、
成長に自身の力量も加味しているのがアクションアドベンチャーだと思っています。
定義が曖昧になってきているのは、それだけゲームの多様性が増してきている証拠ですよね。
作る側も遊ぶ側もゲームに柔軟な考えを組み込めるのは良いことだと思っています。
ぼくと同じような認識ですね。最近はアクションアドベンチャーでも成長要素を加えた作品が増えてきていますが、プレイヤースキル重視という根底がある以上は重要度が低い要素になりそうです。
ゲームも歴史が長くなってジャンルの棲み分けが難しくなってきましたが、そういう時は原点を辿ったら分かるようになります。
似たようなところで、一昔前だとスーパーファミコンの
ゼルダの伝説 神々のトライフォースと聖剣伝説2とかが
好対照で分かりやすくて、よく引き合いに出されてましたね。
RPGの将来のアクション化はドラクエの堀井雄二さんが
ファミコン時代から言われていて、流石の慧眼だなと
こうして実際にその推移を目の当たりにすると
特にそう感じますね。
>ゼルダの伝説 神々のトライフォースと聖剣伝説2
あぁ、これはぼくもよく引き合いに出しました!w
それぞれ似て非なるゲームですもんね。
ただ、初代聖剣伝説はゼルダのフォロワーだったので比べられるのは無理もないかも。
堀井さんの先見性は凄い・・・
アクションアドベンチャーって聞いてもあまりピンとこないんですよね。多分、同じようの人が多いから、アクションRPGというワードがよく使われるんでしょう。実際、面白そうに聞こえるし。
BotWとFFXVは比較対象として分かりやすいですね。神プレイの見応えはアクションアドベンチャーの方が上だと思います。
ソウルライクゲームは、前提として高難易度であることを踏まえて説明しなければならないところがややこしいw他のゲームと比べるとどっちでもなくなってしまいますよねw
これに限らず、もっと分かりやすい言葉があればな〜と思います。まあ、考えても思いつかないんですがwデス・ストランディングはユーザーからはアクションアドベンチャーと呼ばれることになるのかな?
RPGという単語には日本人を惹き込ませる魔力が眠っているように感じますw
なので、昔のぼくは友達に興味を持ってもらうようアクションアドベンチャーでもアクションRPGと言い張っていましたw
アクションアドベンチャーは指を使ってのプレイヤースキルが求められるので動画映えしますね。
ソウルライクゲームは確かに高難易度アクションばかりが全面に出ているせいでややこしいことになっているかもw
デス・ストランディングは見た感じだとアクションアドベンチャーに分類されるでしょうね。
この記事を読んで僕はARPGの苦手意識が薄れ、東亰ザナドゥeX+や妖怪ウォッチ4+やシャイニング・レゾナンスリフレインなどに挑戦し長い時間遊ぶことができました!KENTさん、本記事を書いて下さり本当にありがとうございました!!